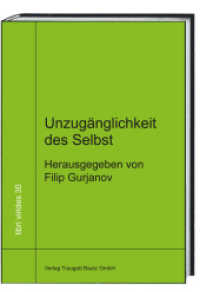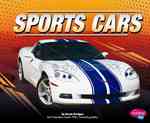内容説明
戦後に生まれ、高度成長期に少年時代を迎えた世代にとって、戦後社会・戦後思想とは何だったか。それは敗戦とその後の民主化を戦後の出発点とした人々の戦後思想史とも違うし、経済や技術の発展に未来の豊かな社会を夢見た世代の戦後思想史とも同じでない。一見すると豊かに見える現代社会のなかに広がる空白感や、「民主的」な戦後社会のなかで目にみえにくい管理が進み、自由な感性や精神を失っていくことをあぶり出す。ほかに「合理的思想の動揺」「日本の伝統的自然観について」を収録する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
26
内山先生は心情を吐露される。「自立した人間として生きようとするとすればするほど個人主義的になってしまう状況、その結果として訪れる孤立と疎外、たとえ意識においては社会から自立しえても現実の行動は社会のなかに取りこまれていくしかない虚しさ、私にとって戦後とはこういうもの」(030頁)。どこか先ほどまでアップしていた鶴見俊輔先生の思想にも通底するところがある。民主主義とは、多数が勝つ制度でしかなかった。しかも多数派なる手段は正しさではなく利益だった。現実は汚れた民主主義と多数派の横暴(054頁)。2021/06/11
武井 康則
8
戦争が終わって反省から政治的なものが求めらえ、社会主義が注目される。それが金銭闘争になり、満足感のなさを疎外と名付けてそれも社会主義が解消してくれると妄信する。著者は1950年生まれ。団塊世代で全共闘世代。飢えて子を売り、戦時中は死ねと言われたのが、モノが充実すると拝金主義だ云々だとよく言うよと今では思ってしまう。信濃毎日新聞に週一で連載されたので章の量が決まっている。結局80年代に入って山村だの共同体だのの思想と言い出す。結局SDGsかよ。80年に席巻したのは構造主義だろ。2025/04/15
-
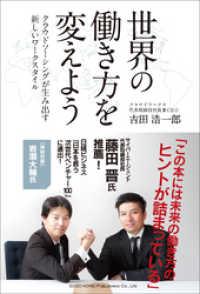
- 電子書籍
- 世界の働き方を変えよう クラウドソーシ…
-
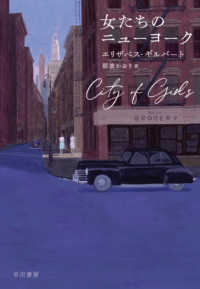
- 和書
- 女たちのニューヨーク