内容説明
天才にして革命家、そして私の師匠――立川談志。
世間からのイメージは破天荒で、毒舌家で、タレント議員の走り。
ただ落語中興の祖として実力派折り紙付きで、圧倒的な存在感を誇った落語家だ。
そんな談志に、大学在学中に弟子入りした立川志らく。
まさに「前座修業とは矛盾に耐えることだ」と言わんばかりの理不尽な試練に耐える下積み修業時代。そして、芸道に邁進し、二つ目、真打ちへと昇進していく日々には、師匠への尽きせぬ憧憬の念と、親子関係をも凌駕する師匠から弟子への愛に溢れていた。
しかし、そんな関係も永遠には続かない。
2011年11月21日、談志は享年75歳、喉頭癌で逝去。
伝統芸能の世界において子弟の別れはない。肉体は消えても、その精神や芸は弟子たちの体に宿り、次代へと伝わっていく。志らくのなかに談志はまだ生きているのだ。
師匠・談志への熱き想いが胸に迫る人気落語家の自伝的エッセイ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いつでも母さん
140
エッセイとあるが、連作短編な感じの全4章。そこにあるのは立川談志愛。私の中の談志さんのイメージ通りだったり、えぇーっ!だったりもして、面白おかしく、ちょいとしんみりして読んだ。志らくさんの本を初めて手にしたが、なかなか良かった(偉そうでごめんなさい) 2023/12/10
J D
71
談志への愛がここにもあった。談春の「赤めだか」を思い出しながら読んでいたが、全く別ものだった。これは、決して電車や飛行機の中で読んではいけない。笑いのスイッチがあちこちに設置してあるから。それも、大爆笑スイッチ。談志の骨を沖縄の海に蒔くシーンは、それはやり過ぎ(書き過ぎ)だろうと思いながらも笑いを止められなかった。また、あちこちで談春のいたずらっ子ぶりが顔を覗かせ飽きさせない。「落語は人間の業の肯定」と談志は言った。だから好きなんだよね。落語。いい読書だった。2024/08/21
fwhd8325
62
家元談志の高座を見ることはできませんでしたが、テレビやラジオで凄さは感じていました。落語協会を脱退してからは、これだけの弟子がいながら孤高の人のような印象も感じていました。家元が志らくをこれだけ可愛がっていたことはあまり知りませんでした。他にもさすが談志の弟子と言わせる方も多く、志らくだけと言うこともないだろうと思います。ただ、以前志らくの「鰍沢」を聴いたときに、それはすごい高座でした。身体が震えたのを覚えています。2024/07/19
佐藤(Sato19601027)
60
7代目立川談志師匠が亡くなって13年目の11月21日。もう13回忌なのかと思うと感慨深い。「芝浜」の高座に感動したことを思い出す。このエッセイは、天国の談志師匠へ向けたラブレターなんだろうな。大学生の新間少年が、池袋演芸場で立川談志の高座を見て入門を決意、志らくの名前を貰って可愛がられた修行時代、真打に駆け上がってからの迷走時代、談志亡き後にテレビの世界へ挑戦する現在まで、その全てに談志師匠への熱い想いが詰まっている。病室での面会場面は、志らく師匠が演じる人情噺のように、涙しながら笑わせてもらった。合掌。2023/11/21
道楽モン
33
立川流の出版が続くなぁ。立川志らくによる師匠・談志との想い出と、自身の修行時代を淡々と綴った作品。文字通り、なんのケレンも無い語り口であるが、これがジワジワ来ます。修行時代を描いた同様の『雨ン中の、らくだ』に比較すると、主観を最小限に抑え、冷静な視点で俯瞰している本作の方が、師匠の偉大さが伝わってきます。いやホント大変なんスから、談志の弟子って。師匠の理不尽さを笑いに転じて語ることがお家芸になっている立川流ですが、どの本もすべてが立川談志という存在の偉大さにたどり着く。師弟関係の絆が強固過ぎて驚きます。2023/11/30
-
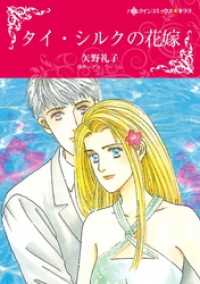
- 電子書籍
- タイ・シルクの花嫁【分冊】 11巻 ハ…
-

- 電子書籍
- 幸せな恋、集めました。【単話】(67)…
-

- 電子書籍
- 【単話売】妖狐+LOVE×Kiss! …
-

- 電子書籍
- ストーリーな女たち ブラック Vol.…
-
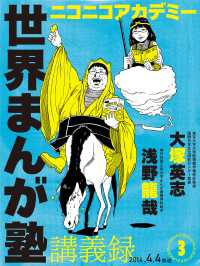
- 電子書籍
- ニコニコアカデミー 世界まんが塾講義録…




