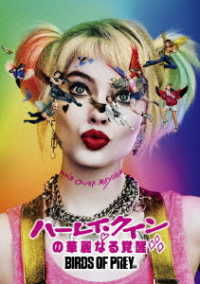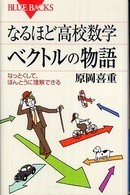- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
富裕層、権力者、急成長企業はシステムをハッキングして成功した。
AI時代にルールを味方につけるには、「正しいハッキングの考え方」が必要だ。
あらゆるシステム(コンピュータ/金融/法律/政治/認知……)はハッキングでき、それは大きな成果を生む。
・ピーター・ティールは10億ドルの資本利得税を支払わずに済んだ。
・グーグルやアップルは税制の抜け穴を利用して多額の税金を逃れた。
・ゴールドマンはアルミニウムを買い占め供給を操作、膨大な利益を得た。
ハッキングとは、システムが新たな環境・展開・技術に適応していく過程である。
強者と弱者では、ハッキングのしかたに違いがある。
強者は、権力を行使する方法のひとつとして使う。
弱者は、権力構造をくつがえすために使う。
規則は破るためにある、とよく言われる。だがそれ以上に、規則は出し抜かれ、悪用され、回避され、裏をかかれる――つまり「ハッキング」される。人間の独創性をとかくゆがんだ意図に利用し、文明社会のよって立つ制度を損ねるこのハッキングという現象を説明するのに、ブルース・シュナイアーほどの適任者はいない。『ハッキング思考』は、現代社会の活力と健全性を奪いかねないこの力について新たな発見をもたらす重要な一冊だ。
――スティーブン・ピンカー(ハーバード大学心理学教授、近著『人はどこまで合理的か』)
本書は、 情報セキュリティの第一人者Bruce Schneier著、A Hackers Mind: How the Powerful Bend Societys Rules, and How to Bend them Back の邦訳です。
目次
第1部 ハッキング入門
第2部 基本的なハックとその防御
第3部 金融システムのハッキング
第4部 法システムのハッキング
第5部 政治システムのハッキング
第6部 認知システムのハッキング
第7部 AIシステムのハッキング
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hitomi
茶幸才斎
カズオ・ハラグロ
Ujiro21
かに