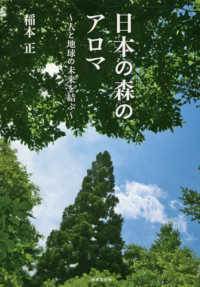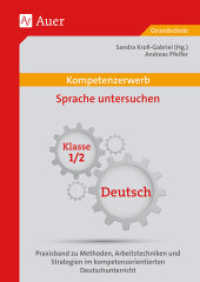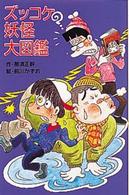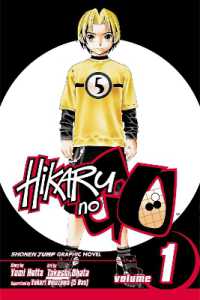内容説明
「技術とは何か?」「技術といかに付き合うか?」ーー古代ギリシャからキリスト教的中世を経て、近代の科学革命、そして現代の最新テクノロジーーー生殖技術、原発、AI……ーーに至るまで、人類数千年の足跡を具体的な事象をベースに辿りながら、普遍かつ喫緊の問題の解答へと迫る、泰斗による決定版・入門書!
不確実で危険に満ちたこの世界を生き延びるための哲学が、ここにある!
[目次]
はじめに
序章 なぜ、現在、技術は哲学の根本問題となるのだろうか?
第一章 人間にとって技術とは何かーープロメテウス神話と哲学的人間学
第二章 宇宙の秩序に従って生きるーープラトンと価値の問題
第三章 自然の模倣ーー古代:アリストテレス
第四章 「無からの創造」の模倣ーー中世:キリスト教
第五章 自然の支配ーー近代:F・ベーコン
第六章 科学革命ーー近代科学の成立と技術の役割
第七章 イデオロギーとしての科学と技術ーー近代のパラドックス
第八章 技術は科学の応用かーー知識論の「技術論的」転回
第九章 技術と社会ーー技術決定論から社会構成主義へ
第一〇章 技術の解釈学ーー変革可能性のために
第一一章 技術の創造性と設計の原理
第一二章 フェミニスト技術論
第一三章 技術との新たな付きあい方を求めてーーJ・デューイとH・ヨナス
終章 技術・事故・環境ーー福島第一原子力発電所事故からの教訓
補論 日本における技術哲学ーー西田幾多郎、三木清、戸坂潤
引用・参考文献
索引
目次
はじめに
序章 なぜ、現在、技術は哲学の根本問題となるのだろうか?
1 技術と現代の生活
2 技術についての哲学/技術という観点からの哲学
第一章 人間にとって技術とは何か
1 哲学的人間学
2 プロメテウス神話
第二章 宇宙の秩序に従って生きる――プラトンと価値の問題
1 技術・経験・価値
2 精密な技術と精密でない技術
3 製作の技術と使用の技術
4 技術と自然
第三章 自然の模倣――古代:アリストテレス
1 プラトンとアリストテレス
2 アリストテレスの技術論
第四章 「無からの創造」の模倣――中世:キリスト教
1 中世キリスト教のもとでの信仰と労働
2 中世ヨーロッパにおける技術の発展と技術観
3 自然の模倣からの脱却
第五章 自然の支配――近代:F・ベーコン
1 ベーコンの分かりにくさ
2 知は力なり
3 進歩の制度化
第六章 科学革命――近代科学の成立と技術の役割
1 科学革命とは何だったのか
2 「思考法の革命」
3 「実験法の革命」
4 「科学革命」の多様性
第七章 イデオロギーとしての科学と技術――近代のパラドックス
1 発明家と科学者の競争
2 科学と技術の制度的分離
3 近代のパラドックス
第八章 技術は科学の応用か――知識論の「技術論的」転回
1 応用科学説
2 「応用」の具体的過程
3 技術知の特有性
4 知識とその「応用」
第九章 技術と社会――技術決定論から社会構成主義へ
1 二つの逸話
2 技術決定論
3 社会構成主義の挑戦
第一〇章 技術の解釈学――変革可能性のために
1 技術/社会の二重側面説
2 技術の「解釈学」
第一一章 技術の創造性と設計の原理
1 「共同行為者」としての技術
2 技術の「他者性」
3 「未知の応用」としての技術
第一二章 フェミニスト技術論
1 フェミニズムの観点から
2 「非本質主義」のラディカリズム
第一三章 技術との新たな付きあい方を求めて――J・デューイとH・ヨナス
1 技術と倫理
2 応用倫理としての哲学
3 責任という倫理
終 章 技術・事故・環境――福島第一原子力発電所事故からの教訓
1 福島第一原子力発電所の事故
2 「想定外」「「原子力村」「安全神話」
3 「想定外」をめぐる解釈の争い
4 技術・事故・環境
補論 日本における技術哲学――西田幾多郎、三木清、戸坂潤
1 技術論論争
2 西田幾多郎
3 三木清
4 戸坂潤
引用・参考文献
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
YO)))
iwtn_
袖崎いたる
ゆうちゃん
zunzun