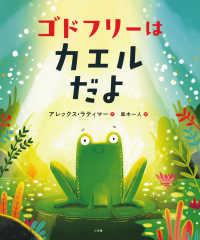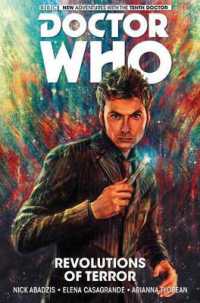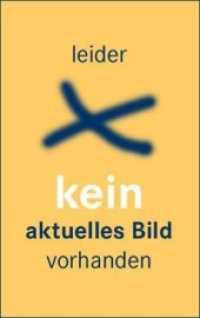内容説明
他者が用いる言葉のダークサイドの力に対抗するためにも、そして自分がダークサイドに陥らないためにも、「悪い言葉」をよく理解しておく必要がある。これまで主流の言語哲学が見過ごしてきた「実社会の言語」の問題に切り込む画期の書。言語哲学が、より開かれたものとなり、真に私たちの哲学になるための一つの大きな契機として。
目次
謝辞
序
第一章 理想化されたコミュニケーション
1─1 七つの典型的な理想化
1─2 手持ちの道具を確認し、実社会に立ち戻る
1─3 いくつかの但し書き
1─4 本書の概要
第二章 言葉を非理想的に使う三つの方法
2─1 逸脱した意図:会話的推意
2─2 なぜ推意にかかずらうのか
2─3 逸脱した意味─前提
2─4 逸脱したスコアボード─文脈のコントロール
2─5 逸脱的なものから悪いものへ
第三章 真理をぞんざいに扱う
3─1 偽なことを述べる
3─2 嘘とミスリード
3─3 真理を尊重することはすべてのコミュニケーションにとって根本的なのか
第四章 でたらめと根深いでたらめ
4─1 でたらめ
4─2 嘘、ミスリード、でたらめからフェイクニュースへ
4─3 根深いでたらめ(つまり、ナンセンスな、意味不明な言葉)
第五章 概念工学
5─1 概念工学への導入:私たちは言葉が何を意味するかを気にかける
5─2 概念工学の主論証(および小史)
5─3 概念工学者にとってのいくつかの課題
第六章 蔑称
6─1 導入
6─2 記述内容説
6─3 前提説
6─4 表出説
6─5 禁止説
6─6 まとめ
第七章 語彙効果
7─1 語彙効果を導入する:言葉の非認知的・連想的効果
7─2 非認知的語彙効果:いくつかの実例
7─3 公の場での議論や理論的研究における語彙効果の利用
7─4 語彙効果の一般理論
7─5 語彙効果はなぜ言語哲学でほとんど無視されてきたのか
第八章 総称文と欠陥のある推論
8─1 導入:総称文とは何か
8─2 総称文の振る舞いについてより詳しく
8─3 いくつかの興味深い実験
8─4 総称文:意味と認識の交わり
8─5 要約
第九章 理想的でない言語行為
9─1 導入
9─2 分散した聞き手
9─3 分散した話し手
9─4 デジタル時代の言語行為
第一〇章 言葉による抑圧と言葉による声の封殺
10─1 言語行為とは何か:手短な導入
10─2 言語的抑圧
10─3 ポルノグラフィーによる言語的抑圧
10─4 声を封殺すること
第一一章 同意という言語行為
11─1 同意の典型例:家の訪問、医療処置、同意書、セックス
11─2 同意に関するいくつかの問い
11─3 暗黙の同意の不精密さ/曖昧さ
11─4 欺きは同意を無効にしうるか
11─5 同意を動的に捉える
11─6 理想化がどのようにして失敗するのかを示す例としての同意
第一二章 言語の理想理論と非理想理論について考える
12─1 理想化された理論はばかげているのか
12─2 予測とガリレイ的理想化
12─3 理解とミニマリストの理想化
12─4 理想化によって何を取り除くべきか
12─5 社会科学における理想理論と非理想理論
12─6 言語の理想理論と非理想理論
訳者解説
1.イントロダクション
2.理論的理想化からの逸脱としての悪い言葉
3.応用言語哲学と言語哲学のこれから
訳者あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こたろう
kuro
maki