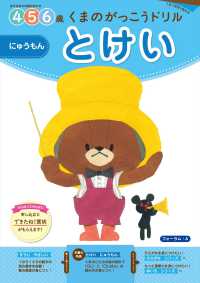- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「英語は学習成功者に学ぶべし」。この鉄則は揺らぐことはない。紹介する嘉納治五郎、夏目漱石、南方熊楠、國弘正雄、山内久明ら8人の〈達人〉は、工夫と努力によって、日本に居ながらにして、英語力の基礎を築き上げた。彼らはまた日本文化への貢献でも傑出した存在である。本書は、〈達人〉たちの英語習得法を紹介するが、それは「英語使い」になる明らかな道筋だ。その過程は、英語受容をめぐる格闘の歴史でもある。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
93
斎藤先生の英語達人の二作目です。8人の英語の達人(嘉納治五郎、夏目漱石、南方熊楠、杉本鉞子、勝俣銓吉郎、朱牟田夏雄、國弘正雄、山内久明)の生涯や業績について詳しく述べられてます。山内先生は存じ上げていないのですが、意外という感じを受けたのは嘉納治五郎でした。勝俣、朱牟田、國弘の諸先生方は著作物でお世話になりました。國弘先生の「只管朗読・只管筆写」という言葉はまさにその通りだと思います。今後は行方昭夫先生や鳥飼玖美子さんやご自身の英語の学習法を知りたい感じです。2023/03/31
Nobu A
16
斎藤兆史先生著書7冊目。2年半前読了の前巻はうろ覚え。臥薪嘗胆を地で行く英語修学の鍛錬にはただただ頭が下がるが、筆者の随所にある冷徹な考察に目が行く。「語学学習と辞書」の関係性は目から鱗。「使える英語」や「多読」が持て囃される昨今、辞書を一度も引かずに語学学習は成立しない。現代の英語教育への提言もある「あとがき」が秀逸。通読で感じたのは粗全員に薫陶を受けた素晴らしい指導者の存在。論理的で格調高い英語を操るにはやはり独学では不可能。習熟度を高めたのは本人の努力だが、木鐸なくして歴史に名を残せなかったはず。2024/01/05
電羊齋
11
あとがきの「達人たちはなにか特殊な修業を行ったわけではない。当たり前の学習法を、とてつもない時間をかけ、とてつもない情熱と根気を持って実践しただけである。」という一文に共感。達人たちは、あくまでたくさん読み、音読し、書き、訳すという語学の基本に忠実であったことがわかりやすく語られている。達人たちの学習法は、自分も中国語という外国語を学ぶ際に大いに参考にしたい。2024/01/15
新父帰る
10
2023年2月刊。同著者の第二弾です。嘉納治五郎が取り上げられていたのにはびっくりしました。私が知らなかっただけのようですが。夏目漱石のことはその経歴から言って想像していました。全く名前の知らない女性の達人もいました。杉本鉞子です。エツコと読むそうです。国広正雄は学生時代に知っていました。達人に取り上げられている人々はどの方も大変努力家でやはり、その努力も尋常ではないですね。著者は彼らの語学学習が今や古典的と見られている事に大変憤りを感じています。それで先人の語学学習法を模範として示したかったのだと思う。2023/03/17
きざはし
9
前作から20年以上。その間に教養学部で斎藤先生の授業を受けることができたのは光栄至極。学生の発音を正すとき、その間違った発音を真似しないこだわりがあったのを覚えている。あと、ジンジャー・ベイカーよろしくドラムを叩いていたのも。前作同様「音読、素読、文法解析、辞書の多様、暗唱、多読、暗記、作文、その他、考えうるかぎり質の高い英語に触れ、それを真似して使う練習をする」ことの重要性を訴える。現代からの人選もあるので、この勉強法が決して神話的な達人にだけ当てはまるわけではないことが説得される。2023/07/15
-
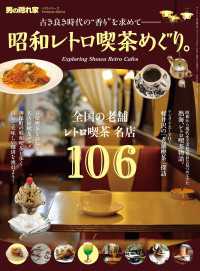
- 電子書籍
- 男の隠れ家 特別編集 ベストシリーズ …
-
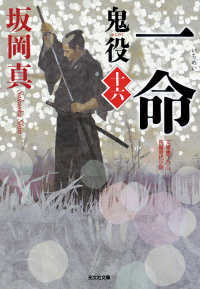
- 電子書籍
- 一命~鬼役(十六)~ 光文社文庫