- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
貧乏なのに、紙幣の顔。生まれは裕福、晩年は借金三昧。いくら稼ぎ、いくら借り、何を買い、何を思ったのか?金銭事情で読み解く、日本初の女性職業作家の新しい姿。
-
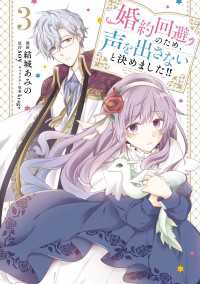
- 電子書籍
- 婚約回避のため、声を出さないと決めまし…
-

- 電子書籍
- 抱かせて下さい聖女様!~年下美男子と性…
-
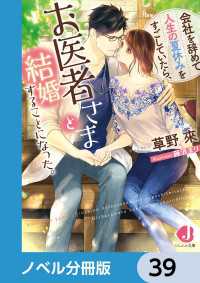
- 電子書籍
- 会社を辞めて人生の夏休みをすごしていた…
-

- 電子書籍
- 幻のかなた【分冊】 10巻 ハーレクイ…
-

- 電子書籍
- 王弟殿下のお気に入り 転生しても天敵か…



