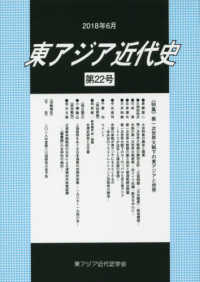内容説明
いまそこに迫る世界食糧危機、そして最初に飢えるのは日本、国民の6割が餓死するという衝撃の予測……アメリカも中国も助けてくれない。
国産農業を再興し、安全な国民生活を維持するための具体的施策とは?
「大惨事が迫っている」国際機関の警告/コロナで止まった「種・エサ・ヒナ」/ウクライナ戦争で破壊された「シードバンク」/一日三食「イモ」の時代がやってくる/国力低下の日本を直撃「中国の爆買い」/「原油価格高騰」で農家がつぶれる/世界の食を牛耳る「多国籍企業」/食料は武器であり、標的は日本/「食料自給率一〇〇パーセント」は可能だ/「食料はお金で買える」時代は終わった/「成長ホルモン牛肉」の処分地にされる日本/ポテトチップスに使われる「遺伝子組み換えジャガイモ」/農政軽視が招いた「人災としての危機」/「日本の農業は過保護」というウソ/有機農業で中国にも遅れをとる/明るい兆しが見えた「みどりの食料システム戦略」/「有機農業&自然農法」さらなる普及を
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねこ
130
米国の研究者が局地的な核戦争が勃発した場合、直接的な被爆による死者は2700万人だが「核の冬」による食糧生産の減少と物流停止による2年後の餓死者は食料自給率の低い日本に集中し、世界全体で2億5500万人の餓死者のうち、約3割の7200万人が日本の餓死者(日本の人口の6割)と推定した。とても強い言葉で筆者は訴えます。それは重要な事なのに耳を傾ける人がとても少ないからです。私は今、世界中で経済戦争真っ只中で日本の旗色はかなり厳しいと感じています。今の円安がその象徴。みんなで力を合わせて乗り越えていかなければ!2023/06/28
MI
117
日本の食料自給率37%、種と肥料の海外依存を考慮すると、10%に届かない。「お金を出せば輸入できる」と国の前提が揺らいできている。農業の現状を知り、愕然とした。特に酪農は政府は「牛乳を搾るな」「牛を処分すれば一頭あたり5万円を払う」と通達を出している。コメや乳製品の輸入を行う一方、牛乳が余ったら、搾るなと。アメリカの自由貿易という無言の軋轢が、日本の農家や畜産などに負担がかかっている。農業再興戦略として、優良事例を紹介していたが、市町や民間レベルではこの負の連鎖は止まらないと感じた。2023/04/07
1.3manen
75
この本は、雑誌『農業経営者』2023年5月号と共に読むとよく分かると思う。どちらの賛否が正しいのか、立場的に全く違うと思いますが、山下先生の指摘から、横井時敬や柳田国男などの農政学の知識も必要です。今の食料危機の問題は、農経の高橋五郎先生の朝日新書も比較しつつ読みたいこの頃です。2023/10/23
ジョンノレン
66
食料自給率37%に種と肥料も加味すると実質の自給率は10%に満たない。更なる気候変動による不作や国際関係の不安定化による不慮の供給途絶による食糧危機を回避する体制整備が必須との問題意識。内向きの農政と財務・経産の消極姿勢に圧倒的な米国の対日穀類・種子肥料飼料等売込み圧力への無策に強い危惧。他方で成長促進剤ラクトパミンやエストロゲン多用の食肉や農薬グリホサート(発ガン、腸内細菌殺す)投入の小麦等、米国の言いなりで輸入。川田龍平議員が超党派で提出のローカルフード法案(地域の種子開発、栽培、循環)に国は冷淡。→2025/03/09
ムーミン
55
想像以上に日本の「農」が危機的状況であることが理解できました。これからの市の施策としても、農業を核とし、農業と結び付けた様々な発展のあり方を考えていかなければならないと、市長と話すことも多くなりました。教育においても、農業とのつながりを「命の教育」「キャリア教育」との関連の中で、これまで以上に意識的に目を向けていきたいと思います。それと関連させ、地域の農業の豊かな発展に繋がり、本当に子どもたちの安全安心な未来を保障する学校給食のあり方についても、よく検討していきたいと思います。2023/01/02
-
![寝取られ令嬢の王子様[ばら売り] 第8話 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1109937.jpg)
- 電子書籍
- 寝取られ令嬢の王子様[ばら売り] 第8…
-
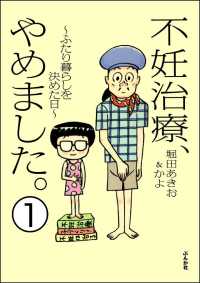
- 電子書籍
- 不妊治療、やめました。~ふたり暮らしを…