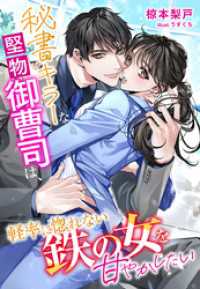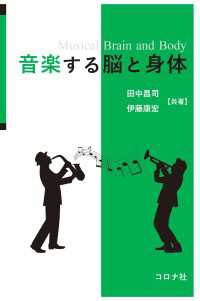内容説明
歴史をどう語るのか。
こぼれ落ちた断片の生が、大きな物語に回収されないように。
戦争体験者の言葉、大学生への講義、語り手と叙述……。
研究者である自身に問いかけながらの試行錯誤と、思索を綴るエッセイ。
【目次】
プロローグ ぎくしゃくした身振りで
1章 パンデミックの落としもの
2章 戦争体験の現在形
3章 大学生の歴史学
4章 一次史料の呪縛
5章 非人間の歴史学
6章 事件の背景
7章 歴史と文学
エピローグ 偶発を待ち受ける
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
50
歴史から学ぶこと。それは、今を考える事、これからを考えることに通じる。書かれている中の「一次資料の呪縛」と「偶発」が心に残る。かねがね、自分で見て、触れて、考えて、自分の言葉で表現することを、忘れないようにしている。表現することで、周囲との接点がうまれ、偶発に通じる。そこは、委ねる部分でもある。それを繰り返す、ひたすら繰り返すことが明日につながると思う。2023/01/07
フム
40
藤原辰史さんの本を読むといつも、大切なことを忘れていたことに気づかされる。読みながら胸の鼓動を意識する。この本もプロローグから心をつかまれた。「ごみを出すのは匿名だから、捨てた人間の卑しさも善良さもそのままあらわれる。」その通りで恥ずかしくなる。パンデミックでも話題だったエッセンシャルワークであるごみを集める人々に多くの思想家や詩人が想像力をかき立てられてきた。ボードレールは『屑拾いの酒』という詩を書いた。「屑拾いがやって来るのが見られる 首をふり よろめき 壁にぶつかる姿は まるで詩人のよう」2023/03/15
Nobuko Hashimoto
37
歴史学に取り組むことについてのエッセイ集。著者が史料から、そして生身の人から日々学び、熟考し、行動し、ときには動揺している様子が書き留められている。日常的で具体的なのだけどどこか霞がかかっているようにも感じられるのはなぜだろう。/学生の要望に応じて新規開講した京大の全学共通科目で、『○○の20世紀』という本を書くとしたらというお題に対する学生の回答を紹介した項が面白い。1回生が圧倒的に多いという科目のはじめの2ー3回目くらいで、そのまま卒論にできそうな問いが立てられていて感心する。2023/05/12
かふ
20
一つのまとめた歴史書ではなく、それらにまつわるエッセイ。まあ、断片のようなものだが、それらはこぼれ話的な屑を拾い集めたものなのだろう。ボードレールの詩でパリの屑拾いはその集めた屑によってその土地の歴史を知るというベンヤミンのボードレールの歴史論から、一見関係なさそうなものが歴史的に繋がっているという。大学の講義から若手研究者時代の資料の集め方から影響を受けた本まで面白い話も退屈な話も。そこから専門家以外の人が歴史の中で自ら関係してくるものが歴史を作っていたり、学ぶべきものがあるという。2024/03/17
kuukazoo
15
歴史とは一次史料の集積に裏付けられた構築物なのだけど普通はできあがったでかいものしか目に入らない。歴史を学び始めの頃はでかいものだけでお腹いっぱいになってしまったり。一方で歴史的人物や出来事を題材とした物語の吸引力はものすごくエンターテインメントとして「大きな歴史」が消費されてたり。そんなものからこぼれ落ちた小さな声に形を与え可視化することも歴史学者の役割なのだろう。歴史の語り方も様々で、そこから受け手が何をどのようにどの程度受け取るのか。歴史修正主義の問題などもなかなか一般には届きづらいのかもしれない。2025/05/31