- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
第二次世界大戦中、女性画家は男性画家と同様に戦争の光景を描いた。当時を生きた長谷川春子、桂ゆき、三岸節子などの足跡を紹介。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ありんこ
3
銃後という言葉を初めて知りました。朝ドラなどで、戦争中の女性がどのように生きたかというストーリーは見たことがありますが、「皆働之図」にあるような仕事のことや、女性画家の立場のことなどを知ることができました。時代の変化によって生き方や働き方が左右されること、その変化の中で自分を見失わないためにはどうすべきか、考えさせられました。2022/10/10
ぴの
2
著者の祖母は戦争の時書かれた絵を見て「なつかしい」と言ったそうだ。そこから話に吸い込まれてく。どうして女流という言葉はあるのに男流という言葉はないのか。戦争を利用して女性の立場を上げていこうとする姿。いろんな角度から戦争を知ることは意味あることだと思う。2015/09/11
ずー
1
戦争に協力するとはなにごとか!と後から言うのはたやすいが、戦時中に女性が働かざるをえなくなった状況(国家の本音としては家父長制を温存しておきたいという状況ではあったが)をある意味利用し、花や子供といったモチーフしか許されていなかった女性画家が「働く女性」を描くことができたという状況に、なんともいえない気持ちになってしまった。また、三岸節子に興味を持った。当時としては(というか今でも)非常に先進的な思想の持ち主で、現代で活躍してほしかったと思う。皆働之図が焼却されずに残ったことに、アーカイブの意義を感じた。2021/12/17
yui
0
今年特に注目されている戦争画、女性画家たちも勿論絵を描いた。女流美術奉公隊による作品に着目し、戦争画における位置付けと、女性画家ないしは、女性そのものに国家が求めていたものを紐解いていく。近代における戦争と美術の流れも把握できるのに新書という読みやすさ。2015/12/01
tkm66
0
着眼点は面白いんだが・・いや、タイトルも・・この〈しっくり来ない感じ〉はなんでしょうね。2015/10/09
-
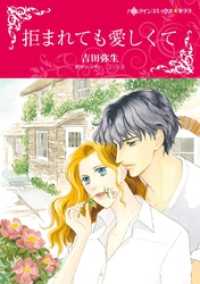
- 電子書籍
- 拒まれても愛しくて【分冊】 2巻 ハー…
-

- 電子書籍
- 拒まれても愛しくて【分冊】 5巻 ハー…
-

- 電子書籍
- ふい~らあ倶楽部 2020年6・7月号
-
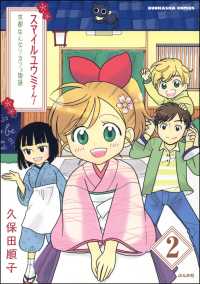
- 電子書籍
- スマイルユウミさん!京都はんなりカフェ…
-

- 電子書籍
- 復興亜細亜の諸問題 下




