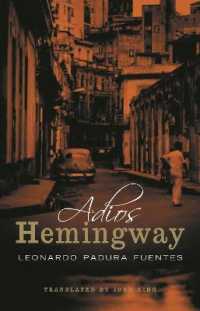内容説明
すべての生物学の土台となる学問こそが、分類学だ!
なぜ、我々は「ものを分けたがる」のか?
人類の本能から生まれた分類学の始まりは紀元前。
アリストテレスからリンネ、ダーウィン……と数々の生物学の巨人たちが築いてきた学問は、
分子系統解析の登場によって大きな進歩を遂げている。
生物を分け、名前を付けるだけではない。
分類学は、生命進化や地球環境の変遷までを見通せる可能性を秘めている。
生命溢れるこの世界の「見え方」が変わる一冊!
地球上で年間1万種もの生物が絶滅しているという。
その多くは、人類に認識すらされる前に姿を消していっている。
つまり私たちは、まだこの地球のことをこれっぽっちも分かっていない。
それどころか、「分かっていないことすらも分かっていない」のである。
だが、分類学を学ぶことで、この地球の見え方は確実に変わる。
奇妙な海洋生物・クモヒトデに魅せられ、
分類学に取りつかれた若き分類学者が描き出す、新しい分類学の世界。
◆主な内容
プロローグ 分類学者の日常
第1章 「分ける」とはどういうことか ~分類学、はじめの一歩
第2章 分類学のはじまり ~人は分けたがる生き物である
第3章 分類学のキホンをおさえる ~二名法、記載、命名規約とは?
第4章 何を基準に種を「分ける」のか? ~分類学の大問題
第5章 最新分類学はこんなにすごい ~分子系統解析の登場と分類学者の使命
第6章 生物を分けると見えてくること ~分類学で世界が変わる
エピローグ 分類学の未来
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
流石全次郎
14
生物の分類。分類学とは何か。その歴史と経緯、分類学の父アリストテレスから、現在の学名を提唱したリンネ。生物学の基盤環境は生物分類学のうえに成り立ってっいるのは明らかではあるけど、その全貌把握はまだまだ。最新の分類学手法や各専門分野の融合化、紆余曲折しながら種の分類を解析していく過程、過去の記載の誤りを補正していく作業。新種発見、新種記載のプロセスなど。突き詰めてゆくと哲学的な領域にはいってゆく生物の種とは何だろうという疑問。いずれも分かり易い内容で素直に読み終えることができました。2022/09/07
うぃっくす
10
カテゴライズが好きなので分類学は大変興味深いんですけどドメインってカテゴリはじめて聞きましたお恥ずかしい。進化の過程や場所(ニッチ)によって生じる些末な差異をどのようにとらえてるのかな、とか、とはいえ分類なんてしなくても生きてけるし科学は進化するのでは?って疑問とかも説明してくれてたので少しだけ分類学が身近になった気がする。新種発見ニュースの影にある地道な積み重ねの努力を知れてよかった。2024/12/03
🍭
7
化学・物理分野の息抜きに生物系の本を読みました。既知の言葉が多いので読みやすかったです。分類学と系統学が扱う部分がマスクしてるって話とか、αβγ分類学の話とか、「分類学とは何か」をわかりやすめ(わかりやすいとは言ってない)に説明していてくれていて面白かったです。学名をつける際の実際の方法や、論文の書き方とかについて触れてるところも好印象です。分子系統解析がつかえる、今後の分類学はどのくらい発展していくのか楽しみだなと思いました。μ、n、f、aの世界へアクセスできる時代ってすごい。2023/11/09
くまくま
7
分類学とは何か、歴史から実際の取り組みまで多面的に知ることができて門外漢でも楽しめた。そもそも種(しゅ)とは何かですら、定義が定まっていないというのは面白い。2022/08/25
桧山
5
ちょっと難しかった。生物の分類って明確に線引きできると思ってたんだが実際はそうではなく、隠蔽種とか面倒くさいのもあると初めて知った。もうちょい個々の生物に興味を持ってから分類学に手を出した方がよく理解できた気がする。2023/07/21