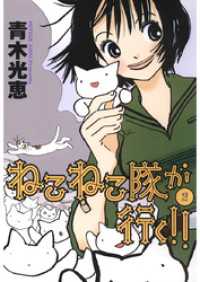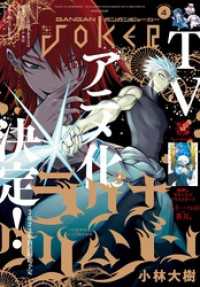内容説明
「誰も望まなかった戦争」がなぜ起きたのか?
1938年9月、ズデーテン危機が戦争に至ることなく「解決」され、戦争熱を全く欠いていた英独両国民は安堵していた。イギリスでは宥和政策がもてはやされ、ドイツでは「水晶の夜」事件が起きた。英国民は戦争に巻き込まれることを恐れながらも現実感を持てないでいた。しかし1939年に入ると国際的な小康状態は終わりを迎える。3月にドイツ軍がチェコに進駐するが、英政府や世論は他人事のように振る舞い、宥和政策を手放せなかった。戦争が間近に迫っていたにもかかわらず、英独両国民は「平和」な生活を営み、戦争は遠い出来事のように感じられた。8月に独ソ不可侵条約が締結され、世界中に衝撃を与えた。もはや英独両国民の意識がどうであれ、ヒトラーのポーランド侵攻は目前に迫っていた。ナチは独国民に対するアリバイづくりのために、また戦争に国民を誘導するために宣伝活動をしていた。こうして9月1日から3日にかけて、凄惨な暴力を伴う大戦への決定的な一歩が踏み出されることとなった……。
第二次世界大戦開戦前の1年間、英独の普通の人びとの日常生活と心情、その変化を英国の歴史家が活写する。新たな侵略戦争が進む現在、示唆に富む書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
32
第2次大戦ヨーロッパ、1938年秋から1年間開戦までの様子を庶民らのリアルな生活史を中心に追う読み応え有り労作。ミュンヘン合意、チェコ・ズデーテンランド併合(独でも戦争反対の声が強かった、クーデター計画もあった)。水晶の夜(パリでのユダヤ青年テロがきっかけ)、チェコスロバキア解体併合(ポーランドも火事場泥棒的侵略を実行)、ポーランド侵攻(ナチの汚い工作、ポ側のドイツ人虐殺)、英仏戦争宣言まで。「戦争は嫌だ」庶民の声が、政権のプロバガンダ、ペテン、面子で押しつぶされる様が生々しい。現代でも変わりない問題だ。2022/10/11
バルジ
2
ミュンヘン会議からポーランド侵攻までの一年間を政治指導者・一般市民の視点から描く良書。副題の通り「誰も望まなかった」戦争はどのような経緯で発生し、かつ一般市民の視座を取り入れることで人々は戦争に対してはどのような感情を抱いたのか複層的に論ずる。ミュンヘンの「宥和」以降、戦争の危機は去ったかのように見えた。人々は備えながらもなお戦争には懐疑的でありまた避けられると見ていた。これは英独双方に共通する。しかし危機は創り出されプロパガンダの大波に攫われると人々は受け入れてしまう。2022年でも見た光景である。2023/05/06
あらい/にったのひと
1
2025年に読むと、やはり現在との類似点に目が行ってしまうのではなかろうか。デマは社会の敵なわけですが、それを認識するのは難しいのかもしれない。権威から飛んでくるデマもあるわけだし…ついったなどSNSはたくさんありますが、こまめにその時の感情を記録しておいて、後で追えるようにしておく方がいいのかもしれませんね。日記を書くでもいいのだけど。あ、本自体の内容も文句無しによいものでした。2025/03/05
吉田よしこ
0
★★★★★2024/07/31
koba23
0
第二次世界大戦前夜の様子がリアルにわかる本。ナチス体制ドイツが迫害されるドイツ民族を救うために侵略しているところなど、現在のロシアと酷似しており戦慄した。またできれば戦争したくない雰囲気がありつつ戦争に突入していく様子など、これも2023年現在と似ており憂鬱になった。2023/02/23