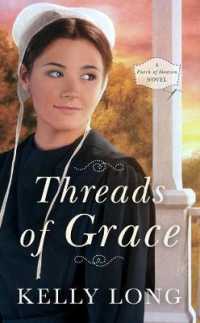内容説明
若くして首相に上りつめ、昭和の政界で絶大な存在感を持ち続けた田中角栄。そんな彼の代表的な政策提言である『日本列島改造論』は、1972年に刊行されてから、今年で50年目を迎える。この書のなかで、角栄は日本列島における鉄道の重要性を訴えた。続々と実現している整備新幹線網はまさにそのひとつ。しかし、角栄が重視していた地方ローカル線は、国鉄末期の経営再建、1987年の国鉄の分割・民営化、2011年の東日本大震災など、その時々で窮地に立たされてきた。この50年間で、角栄の提言はどのように生きているのか。今、解き明かす。
目次
目次
第一章 「日本列島改造論」とその時代
第二章 高速新幹線ネットワークの 50 年
第三章 地方ローカル線 50 年の興亡
第四章 『日本列島改造論』 が遺したもの
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nishiyan
12
『鉄道と国家-「我田引鉄」の近代史』で鉄道と政治の関係を取り上げた著者が田中角栄『日本列島改造論』から新幹線と在来線、地方ローカル線の関係を紐解く新書。田中角栄がどのような視点で鉄道を考えていたのかよくわかった。新幹線網の整備によって浮いた在来線の旅客分のところに貨物輸送強化に充てるという考えは興味深かった。国鉄民営化以降、国の鉄道政策は揺れ動いている。この先、50年100年を見据えたものが出てくるのだろうか。『日本列島改造論』で掲げられていた政策が今も影響を及ぼしていることを知り、そんなことをふと思た。2022/09/05
kenitirokikuti
9
とても気になる内容だったので、結論部分を先読みした▲まず、角栄列島改造論のビジョンは国鉄の存在が前提だったこと。いま思いついたが、『銀河鉄道999』と『シンカリオン』の差、とか/かつて飛行機と鉄道の料金差は大きく、特に飛行機には子ども料金がなかったので、家族の帰省は鉄道(特急や夜行)が主だった。平成になって、新幹線と飛行機が競合するようになった/裏日本、西日本では在来線が虫の息である。山陰から山形へ行くには、東京を経由した方が早い。新幹線が東京中心なので、新潟から秋田へも同様。2022/08/07
月猫夕霧/いのうえそう
8
田中角栄の列島改造論に書かれている鉄道の施策について、その後の50年間の鉄道の歴史と照らし合わせて列島改造論の影響の有無を答え合わせしていくような感じの内容でした。新幹線は1985年までにやるはずのことが2045年までかかりそうですが一応目標達成なんでしょうかね。行政が一度決めたことを変更することが難しいというのは承知してますが、民営化という大変革をしても新幹線は変更されずというのは言われてみる驚きで、変革の難しさを改めて感じます。2023/01/16
西澤 隆
8
たぶん都市部在住のひとが読むと全くちがう感想があるはず。おそらく今の中国の西の奥の方と上海や深センの差のように、おなじ国だとは言えないほどの生活の差、それも生活の豊かさの差ではなく「生存可能性の差」が田舎と都会には厳然として存在した時代。過密と公害等を抱えた都市部からいろんなリソースを田舎に環流させて少し平準度を上げ、田舎も豊かにしようという願いがひしひしと伝わってくる。「論」の検証というよりは論を実践するために作った法律という仕組みの堅固さの検証ともいえる本書。随所に「かっちりやる」仕事の凄さを見ました2022/08/28
ミチ
6
日本列島改造論と鉄道は切っても切り離せない事のように思う。今や東京一極集中し地方は置き去りで過疎化は進む。若者は気軽に東京に行きそのまま東京に骨を埋める。日本経済の活気は東京あってこそだがこの先鉄道はリニア含めどうなるのだろうか。2024/03/06