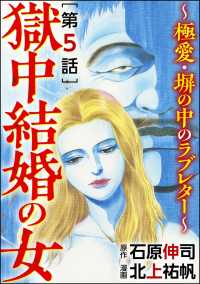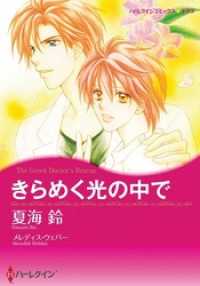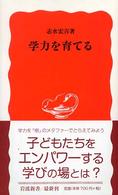内容説明
映画、マンガ、アニメ、ゲーム、テレビドラマ、ウェブサイト――活字で書かれた小説でなくても、現代文化では様々なメディアを通じて物語が発信され、受容されている。多様な表現ジャンルの価値がフラットになるいま、小説にはどのような可能性があるのか。
現代の小説の枠組みを確認するために、マンガやアニメ、ゲームなどのサブカルチャーを雑食的に取り入れて発展・成熟を遂げてきたライトノベルの方法や様式を検証する。そのうえで、ジャンル間を越境してコンテンツを接続するメディアミックスのあり方、図書館や教育での小説の位置、ジェンダーや2・5次元との関係性などを照らし出す。
小説が現代の多様な文化のなかで受容者を獲得し拡張する可能性、サバイブする戦略を、多角的な視点から解き明かす。
目次
はじめに 大橋崇行
第1部 拡張する現代小説
第1章 現代文芸とキャラクター――「内面」の信仰と呪縛 大橋崇行
1 マンガを小説で表現する――恩田陸『蜜蜂と遠雷』
2 直木賞における評価と作中人物の「内面」
3 現代文芸におけるキャラクターの越境
第2章 キャラクター化される歴史的人物――「キャラ」としての天皇・皇族の分析から 茂木謙之介
1 歴史と物語、現在における切断
2 特異「キャラ」としての近代天皇
3 平成末期、天皇キャラの乱舞
第3章 霊感少女の憂鬱――ライトノベルと怪異 一柳廣孝
1 ラノベと怪異
2 ラノベ独自の「怪異」表象とは何か
3 「霊感」と「霊感少女」の起源
4 ラノベのなかの「霊感少女」たち
第4章 「太宰治」の再創造と「文学少女」像が提示するもの――『ビブリア古書堂の事件手帖』シリーズ 大島丈志
1 『ビブリア古書堂』シリーズと太宰治『晩年』
2 「断崖の錯覚」の再創造
3 太宰治「断崖の錯覚」から『ビブリア古書堂』シリーズへ
4 『ビブリア古書堂』シリーズと「文学少女」が提示するもの
コラム ライト文芸 大橋崇行
コラム ウェブ小説からみる出版業界の新しい形 並木勇樹
コラム 中国のネット小説事情――「起点中文網」のファンタジーカテゴリー「玄幻」を中心に 朱沁雪
第2部 創作空間としてのメディア
第5章 遍在するメディアと広がる物語世界――メディア論的視座からのアプローチ 山中智省
1 「読んでから見るか、見てから読むか」の現在
2 多様で複雑なライトノベルをめぐるメディアミックス
3 「アダプテーション」が発生するポイントはどこか
第6章 三つのメディアの跳び越えかた――丸戸史明『冴えない彼女の育てかた』を例に 山田愛美
1 「会話劇」としての『冴えない彼女の育てかた』
2 挿絵の活用
3 アニメとの比較
第7章 学校図書館とライトノベルの交点――ライトノベルは学校図書館にどのような可能性をもたらすのか 江藤広一郎
1 中学・高校図書館とライトノベル
2 これまでの教育空間とライトノベル
3 今後の学校図書館とライトノベル
4 ICT教育とライトノベル
コラム 学校教育を取り込むライトノベル 佐野一将
コラム ライトノベルで卒業論文を書く人へ――「ぼっち」がメジャーになる瞬間 須藤宏明
コラム ラノベ編集者の仕事 松永寛和
コラム VRがもたらす体験 山口直彦
コラム ライトノベルとメディアミックス――特にアニメ化について 芦辺 拓
第3部 文化変容とジェンダー
第8章 ライトノベルは「性的消費」か――表現規制とライトノベルの言説をめぐって 樋口康一郎
1 ライトノベルの表紙は「暴力」か
2 オタク文化と表現規制
3 表現規制の問題点
4 表現規制問題を批評するライトノベル
5 PC/SNS時代の「公共」
第9章 「聖地巡礼」発生の仕組みと行動 金木利憲
1 聖地巡礼とはどのような現象か
2 ビジュアル情報と聖地巡礼
第10章 少女小説の困難とBLの底力 久米依子
1 少女小説の直面する困難
2 現代日本と少女小説のルール
ほか