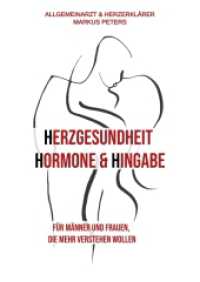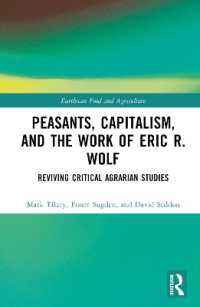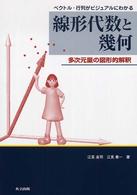内容説明
デジタル経済の急速な進化に伴い、知財の保護と利用の自由のバランスを根本的に見直す必要性が叫ばれるなか、学際的研究のニーズが高まっている。知財法学者はもとより、法哲学者、憲法学者、情報法学者、民法学者、政治学者、文化人類学者、経済学者、実務家らが一堂に集い、知財制度の根幹に迫る。
目次
第5編 知的財産とイノベーション
第14章 職務発明制度とイノベーション──基本的構造の頑健性と合理性[中山一郎]
I はじめに
II 職務発明制度の変遷と基本的構造
III 職務発明制度の基本的構造の合理性
IV おわりに
第15章 創薬イノベーションに向けた特許制度と薬事法制の協働[前田 健]
I はじめに
II 創薬のインセンティブ確保の重要性とその手段
III 特許制度と薬事法制の協働による独占の実現
IV 独占による収益──薬価基準の意義
V おわりに──俯瞰的な制度設計の必要性
第6編 知的財産と産業実態
第16章 標準必須特許の権利行使とホールドアップ──経済学と競争政策の視点から見たFRAND条件の意義と課題[岡田羊祐]
I はじめに
II ホールドアップ問題
III 特許ホールドアップの危険性を高める要因
IV 標準必須特許を巡る問題の所在
V 特許侵害訴訟における差止請求の制限と損害賠償請求
VI おわりに
第17章 コンテンツ産業と著作権活用──迫る危機とビジネスの変容[河島伸子]
I はじめに
II コンテンツ産業の伝統的価値連鎖モデルとその変容
III 従来型コンテンツ・ビジネスへの脅威
IV アーティストへの影響
V コンテンツ・ビジネスの対応と変容
VI おわりに
第7編 知的財産と実証研究
第18章 知的財産制度はどのように利用されているのか──いくつかの知的財産に関する実証研究とその含意[渡部俊也=吉岡(小林)徹=平井祐理=胡韋]
I はじめに
II 特許侵害訴訟における損害賠償額に関する実証研究
III 営業秘密の保護
第19章 特許の有効性判断に対する第三者の貢献──安定的な特許権の重要性[中村健太]
I はじめに
II 特許権の安定性
III 我が国制度の概要と変遷
IV 第三者の貢献──直接的効果と間接的効果
V 特許の無効化とイノベーション
VI おわりに
第8編 知的財産と国内政治
第20章 知的財産権法に関する立法プロセスと課題[別所直哉]
I はじめに
II 改正の手続
III 立法プロセスの端緒
IV 立法プロセスの始まり
V 閣議決定へ
VI 国会での審議
VII 次の課題の萌芽
VIII 立法プロセスの不透明性
IX 政策目標の実現はできたのか
X 立法事実重視に向けて
第21章 著作権法の政策形成およびルール形成が抱える課題について──一般条項型の権利制限規定のあり方に焦点を当てて[小島 立]
I はじめに
II 平成24年の著作権法改正について
III 著作権法の政策形成およびルール形成が抱える課題──一般条項型の権利制限規定に焦点を当てて
IV おわりに
第22章 著作権法をめぐる国内政治の政治学的分析──違法複製ファイルへのアクセスに関する法整備をめぐる政治過程の比較分析[京 俊介]
I はじめに
II 先行研究の検討と本章の位置付け
III 比較事例分析
IV おわりに
第9編 知的財産と国際政治
第23章 「TRIPs」の共有知識化の主体・構造・過程[遠矢浩規]
I はじめに
II 分析枠組
III 「TRIPs」の共有知識化──米国から日本へ
IV 結語
ほか