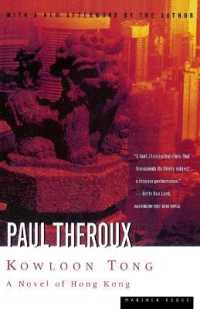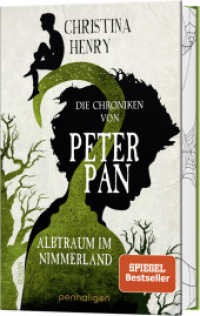内容説明
双極性障害の家族を持ち自身も発症の疑いを持つ大学生、唯(ゆい)は大学のサークル活動を起点として自助グループの運営にかかわるようになり、当事者研究とオープンダイアローグ(OD)を学んでいく。発達障害、吃音、摂食障害、LGBT、鬱、ひきこもりの親など、自助グループに登場するさまざまな困りごとを抱えた当事者たちのケースを通して、この物語は、対人援助職、当事者向けの実践的ケーススタディとなる。
一方で、物語は成長して大学で教鞭をとる唯先生による講義編へと展開する。
講義編では、「ユーモア」「苦労の哲学」「ポリフォニー」「中動態」などのキーワードを並べつつ、当事者研究、ODを基礎から丁寧に解説。さらに、ハイデガー、アーレント、バフチンの思想が交差する深みへと進む。
本編のほか、ほがらかタッチのへたうまイラストや、付録には「唯のひらめきノート」、荒唐無稽なゲームブックなどが収録され、読者はユニークな世界観を味わいながら、当事者研究とODを楽しく学ぶことができる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆいまある
91
不思議な本。18歳の大学生、唯が、自助グループに関わりオープンダイアローグと当事者研究を組み合わせたセラピーを作ろうと奮闘するラノベ風小説。筆者の実体験に基づいており、おっさんが若い女性になりきっている訳だが、コミカル過ぎて嫌悪感は無い。背景についても詳しく、フランクリンまでは成程と思って読めるがハイデガーの名前が出てきた辺りで目が素通りする。実際の治療に役立つ知識も多く参考になる。が、繊細に寄り添う語り方というのは相手を退行させてしまうこともあり、精神科外来の現場では相手を選ぶなあ。2023/02/21
ネギっ子gen
52
当事者研究とオープンダイアローグのミーティングは、どうすれば実践できるかを、自助グループ会合を舞台に、双極性障害の家族を持つ大学1回生・唯を中心に物語形式で紹介――。遊び心に溢れた本で、小説風、対話、講義、質疑応答、マンガ、詩、へたうまイラスト、アイデア集、ゲームブックなどを実装し、巻末には参考文献。著者自身は、ASDやADHDを診断された患者で、LGBTの要素もありアダルトチルドレンや新興宗教2世などの当事者。いくつもの自助グループを立ち上げた、文学・当事者研究を専門とする大学准教授でもある。推し本。⇒2023/02/27
エガ
1
当事者研究、ナラティブセラピー、オープンダイアログ 様々な手法を実践しているストーリーと講義が交互に描かれていた。 オープンダイアログが中動態にとりさらわれること AA、NAなども出てくるしエピトテクス、ハイデガーも出てきた。 様々な手法の底に流れている同じ鉱脈を探す話だったように思う
NoDurians
1
図書館でピックアップされていて借りる。取っつきやすくはあるけれど、基礎的な知識がないので、なかなか「分かった」には至らなかった。2023/01/13
yuka16611
1
とても自助会についてわかりやすかったです。2022/04/27
-
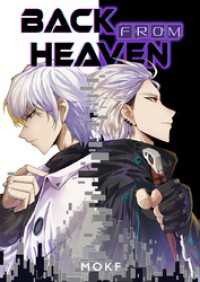
- 電子書籍
- ふりだしから始まる覚醒者【タテヨミ】第…
-
- 洋書
- Kowloon Tong