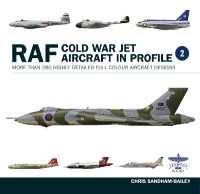内容説明
「茶」を軸として、織田信長・豊臣秀吉、二人の天下人の戦略を読み解いた、新しい戦国史!
室町から戦国にかけて、武士の文化として発展した「茶」。しかし、それは一方で政治のツールとしても活用されました。
なかでも信長は「名物」とされた茶道具を家臣たちに分け与えることで、自らの信頼の証とし、家臣統制に活用します。またそれは外交のツールでもあり、茶の文化をリードした堺の商人たちと深く交わる手段でもありました。
そのなかで、信長に重用された一人が、千利休であり、信長の戦略を継承したのが秀吉だった、と著者は説きます。
では、なぜ堺の商人のなかでも後発だった利休が重用されたのか? そして秀吉の側近として盤石の地位を築いたかに思われていた利休が突然失脚したのか?
著者の田中氏は大日本茶道学会会長、公益財団法人三徳庵理事長として茶道文化普及に努めるかたわら、徳川林政史研究所や徳川美術館で歴史・美術を研究。茶の道に精通した著者ならではの視点が光ります。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
98
帯の通りの事を思ったのは織田信長が生きている間のこと、「茶湯御政道」の時代は余りにも短いものであったのです。最近の織田信長の再評価は実に多くの本でも取り上げられていますが、この本でも、織田信長の茶道に対する評価の保守性が挙げられています。そして、豊臣秀吉の時代には、「茶湯御政道」は頂点を迎え、そして、千利休の死により、唐突な終わりを迎えます。聚楽第行幸で「天皇を饗す力」を見せ付けた豊臣秀吉は「内々の儀」を任せていた、千利休を自裁させます。今までの利休の死因としては一番腑に落ちました。身も蓋もない話ですが。2022/06/07
sasara
18
名物茶道具を権力で収集土地の代わりに恩賞に使い人事掌握信長だったが家康もてなす茶会の前に光秀の謀叛により貴重な唐物を集めた安土城とともに焼失。朝廷に認めて貰いたい一心で金の茶室、北野大茶会開催し野望達成秀吉は目的を果たしたので邪魔になった策略家利休に切腹命令し茶道が完成。侘び寂びの裏はドロドロ権力闘争でした。2022/04/20
フク
16
#読了 よくわかる御茶湯御政道。 黄金の茶室や利休の処断などに対する独自視点の解釈は面白い。 「我が仏 隣の宝 聟舅 天下の軍 人の善悪」はよく覚えておきたい。 図書館。2022/04/06
Sakura
14
公家が知らない分野で勝負すれば馬鹿にされることはない。これを狙って武士によって育まれた文化が能楽であり、茶である、という。お茶会の主役は茶道具であることは知っていたが、これが、誰が持っていたもので、今誰が持っているか、それを知らしめる為に信長が始めた、という話で合点がいった。茶会を政治利用していた秀吉が、関白となった後には最早茶会を利用する必要がなくなった為に利休の存在価値がなくなった、というのも妙に納得がいく。色々と面白かったです。2022/11/11
fseigojp
12
お茶の道が室町から安土・桃山にかけて武家の教養となっていった過程が面白かっった 江戸時代には煎茶道がでてきた このあたり連歌から徘徊、能楽から歌舞伎とよく似ているような2022/04/21