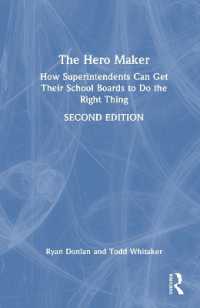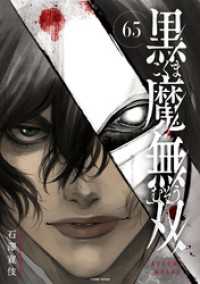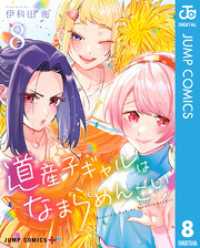内容説明
何があればその生物に「意識」があるといえるのか? 多くの研究者がこの「進化の目印」を求めている。神経機構か、感覚器官か。否。「学習」こそがカギだと喝破する著者二人は、脊椎動物、節足動物、頭足類をも射程に捉え、意識がカンブリア爆発と同時に進化したと推定する。動物意識の源流へと向かう緻密な探究をともに追随する体験!
目次
II 心の進化に起こった、いくつもの重大な移行
第六章 神経への移行、最低限の意識を構成する部品
神経への重大移行──新たな情報システム
最初の神経系と、それを備えていた動物
刺胞動物での前身と実現可能化システム──全体感覚と非連合学習
刺胞動物に制約下連合学習はあるのか?
主観的体験の構成部品?
第七章 連合学習への移行──第一段階
連合学習──区別と段階
オペラント条件づけと古典的条件づけの区別──進化の視点
連合学習の進化的起源に関する初期の見解
学習の進化──細胞と分子のメカニズム
階層をずっと下降する──細胞記憶と神経記憶の関係
制約下連合学習の進化
制約下連合学習する動物は最低限の意識を備えているか?
第八章 無制約連合学習への移行──サイコロの重心をずらす方法
モデルを通した学習──結び合うパターン
階層的推論を通した情報の統合
無制約連合学習のトイ・モデル──その機能的特徴
カテゴリー化し、動機づけを行う感覚状態としての心的表象
無制約連合学習とそれを支える構造の分類学的な分布
制約下連合学習から無制約連合学習へ──発生神経モジュールの重複と新奇なエングラムの使用
第九章 カンブリア爆発と、その魂あふれる派生
エディアカラの園からカンブリアの軍拡競争へ
カンブリア爆発の数多くの原因
行動や学習に駆動された可塑性の進化
ストレスと学習、そして両者の共進化
ポパー型生物の進化
第十章 ゴーレムの苦境
基本前提に立ち返る
細胞の認知、意識を備えた生
ゴーレムの苦境
理性霊魂の進化
原注
訳注
訳者あとがき
図の出典
引用文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yooou
プロムナード
gachin
黒豆
mim42