内容説明
正義とはなにか――
ロック、ルソー、カントに代表される社会契約の伝統的理論を受け継ぎ、功利主義の「最大多数の最大幸福」に取って代わる、著書が構想した“公正としての正義”とは…
「政治哲学の巨人」ロールズの古典的名著。
「個人のかけがえなさと自由が認められること、社会が誰にとっても暮らしやすいものであること」
目次
改訂版への序文
序文
第一部 理論
第一章 公正としての正義
第1節 正義の役割
第2節 正義の主題
第3節 正義の理論の中心理念
第4節 原初状態と正当化
第5節 古典的功利主義
第6節 付随する複数の相違点
第7節 直観主義
第8節 優先順序の問題
第9節 道徳理論に関するいくつかの所見
第二章 正義の諸原理
第10節 諸制度と形式上の正義
第11節 正義の二原理
第12節 第二原理の複数の解釈
第13節 デモクラティックな平等と格差原理
第14節 公正な機会均等と純粋な手続き上の正義
第15節 予期の基礎としての社会的基本財
第16節 関連する社会的地位
第17節 平等を求める傾向
第18節 個人に関する原理―公正の原理
第19節 個人に関する原理―自然本性的な義務
第三章 原初状態
第20節 正義の諸構想の擁護論の性質
第21節 複数の選択候補の提示
第22節 正義の情況
第23節 正の概念の形式的諸制約
第24節 無知のヴェール
第25節 当事者たちの合理性
第26節 正義の二原理にいたる推論
第27節 平均効用原理にいたる推論
第28節 平均原理にまつわるいくつかの難点
第29節 正義の二原理を支持するいくつかの主要根拠
第30節 古典的功利主義、不偏性、そして厚意
第二部 諸制度
第四章 平等な自由
第31節 四段階の系列
第32節 自由の概念
第33節 良心の自由の平等
第34節 寛容および共通の利益
第35節 不寛容派に対する寛容
第36節 政治的正義と憲法
第37節 参加原理に対する諸制限
第38節 法の支配
第39節 自由の優先権の定義
第40節 <公正としての正義>に関するカント的解釈
第五章 分配上の取り分
第41節 政治経済学における正義の概念
第42節 経済システムに関する若干の所見
第43節 分配的正義の後ろ盾となる諸制度
第44節 世代間の正義の問題
第45節 時間選好
第46節 優先権に関する追加的なケース
第47節 正義の諸指針
第48節 正統な予期と道徳上の功績
第49節 混成構想との比較
第50節 卓越性原理
第六章 義務と責務
第51節 自然本性的な義務の原理の擁護論
第52節 公正の原理の擁護論
第53節 正義にもとる法を遵守する義務
第54節 多数決ルールの位置づけ
第55節 市民的不服従の定義
第56節 良心的拒否の定義
第57節 市民的不服従の正当化
第58節 良心的拒否の正当化
第59節 市民的不服従の役割
第三部 諸目的
第七章 合理性としての善さ
第60節 善の理論の必要性
第61節 いっそう単純な事例に即した善の定義
第62節 意味に関する覚え書き
第63節 人生計画に即した善の定義
第64節 熟慮に基づく合理性
第65節 アリストテレス的原理
第66節 善の定義を人びとに適用する
第67節 自尊、卓越および恥辱
第68節 正と善との間のいくつかの相違点
第八章 正義感覚
第69節 秩序だった社会という概念
第70節 権威の道徳性
第71節 連合体の道徳性
第72節 原理の道徳性
第73節 道徳的情操の特徴
第74節 道徳的態度と自然本性的態度との結びつき
第75節 道徳心理学の原理
第76節 相対的安定性の問題
第77節 平等の基礎
第九章 正義の善
第78節 自律と客観性
第79節 社会連合という理念
第80節 嫉みの問題
第81節 嫉みと平等
第82節 自由の優先権の諸根拠
第83節 幸福と有力な人生目的
第84節 選択の一方法としての快楽主義
第85節 自我の統一性
第86節 正義感覚の善
第87節 正当化に関する結語
訳者あとがき-『正義論』の宇宙、探訪
対照表
事項索引
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
ころこ
buuupuuu
やまやま
イボンヌ
-
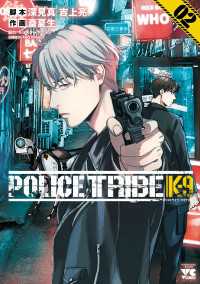
- 電子書籍
- POLICE TRIBE K-9 2 …
-
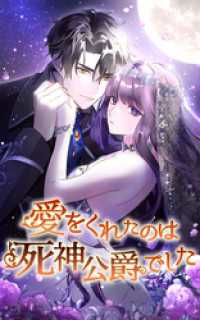
- 電子書籍
- 愛をくれたのは死神公爵でした 35話「…
-

- 電子書籍
- 武道と日本人 世界に広がる身心鍛練の道…
-

- 電子書籍
- 日本全国おとなの絶品美女めぐり(分冊版…
-
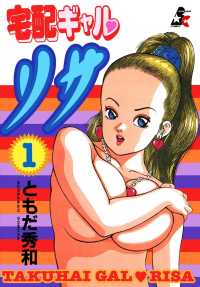
- 電子書籍
- 宅配ギャル リサ 1巻




