- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
2016年春、東京で「ひきこもり女子会」が開かれた。訪れたのは、「介護離職を機に家から出られなくなってしまった」「男性のいる場に行くのが怖い」という、ひきこもりの女性たちだ。「主婦」や「家事手伝い」に分類されてきた、「見えないひきこもり」が可視化された瞬間だった。ひきこもりには女性も性的少数者もいるし、困窮する人も、本当は働きたい人もいる。そして、それぞれに生きづらさを抱えている。ひきこもり当事者の著者が、「ひきこもり1686人調査」と自身の体験をもとに、ひきこもりの真実を伝える。
目次
はじめに
第一章 ひきこもり1686人調査
「ひきこもり・生きづらさについての実態調査2019」
ひきこもりは外出しない?
ひきこもりは若い男性?
ひきこもりは楽?
ひきこもりは働きたくない?
親が裕福だからひきこもれる?
ひきこもりと性的マイノリティ
ひきこもりは何も考えていない?
コロナ禍におけるひきこもり・生きづらさについての調査2020
『ひきこもり白書2021』
第二章 ひきこもり女子会
1 女性のひきこもり
現代女性が受けるプレッシャー
女性のひきこもり・生きづらさについての実態調査
特有の生きづらさ
身体の不調や暴力の被害
介護するひきこもり女性
女性限定の当事者会
2 ある日のひきこもり女子会
「ひとりではない」と思える居場所
「ひきこもりUX女子会」とは
運営で工夫していること
ひきこもりUX女子会に参加して
3 全国で女子会を
自治体・民間団体との連携
広域連携女子会
自分たちで女子会を
オンライン女子会
今後の課題
コラム 女子会参加者・桐谷沙耶さん(仮名)インタビュー
第三章 画一的な支援の課題
1 調査から浮き彫りになった支援の課題
支援に傷つけられる人たち
支援を受ける側の声
どんな支援が良い支援か
2 これまでのひきこもり支援
就労支援じゃない
ひきこもりと事件報道
支援の流れが変わった
プラットフォームをつくる
ひきこもり当事者やその家族と支援領域のプラットフォーム「Junction」
3 支援者に伝えたいこと
まなざしと姿勢
「向き合う」のではなく「横に並ぶ」
支援はいらない、ほしくないという気持ち
ゴールは本人にしかわからない
就労支援は必要か
就労の何が困難なのか
やってみたい仕事がある
当事者活動にこそ支援を
「早期発見・早期介入」への違和感
アウトリーチへの危惧
4 安心できる「居場所」
なぜ「居場所」が必要か
いつでも戻れる「居場所」
「居場所」の課題
イベント運営などの際の工夫
コロナ禍における支援
5 自治体や地域に伝えたいこと
自治体に求める役割
求められる社会的な支援とは
男女共同参画センター横浜南の取り組み
大阪府豊中市の取り組み
第四章 私はなぜ
どのようにひきこもったのか
1 「不登校」のない時代に
〝良い子〟の転校生
教師や親との距離
荒れる中学が楽しい
入学式での予感
あらゆる身体症状
「もうこの場にいることはできない」
高校中退
青春期内科、入院
通信制高校編入学と大検
2 人とつながる
大学も中退
不登校経験者との出会い
アルバイトを始める
カウンセリングを受けたい
3 自分と向き合う
母との関係
「私には自分がない」
家族との軋轢
あきらめるということ
学校への違和感
再びひきこもる
ただ、生きる
恐怖と息苦しさのなかで
4 二つの転機
自分だけじゃないかもしれない
「ひきこもりについて考える会」
八人目の主治医
親元を離れて
当事者発信開始
ひきこもりUX会議発足
今、思うこと
第五章 家族にどうしてほしいのか
1 家族とのかかわり
実態調査から見る家族関係
当事者に見えている世界
家族の関わり方
2 親にしてほしいこと
ポジティブなメッセージを送ってほしい
NGワードとOKワード
「わかり合えない」から始める
本人のことは本人に聞く
親には親の人生を生きてほしい
親が変わると子も変わる
社会に目を向ける
本気で向き合うとは
家族支援の必要性
3 私と家族
父について
妹たち
兄弟姉妹について
コラム そのとき、妹はどう思っていたか
おわりに その船の舵はあなたのもの
付録1 調査やアンケートの自由記述
付録2 不登校・ひきこもり関連団体リスト
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆいまある
こばまり
のんぴ
白ねこ師匠
Mc6ρ助
-

- 電子書籍
- あなたのハニーは転生から帰ってきた【タ…
-
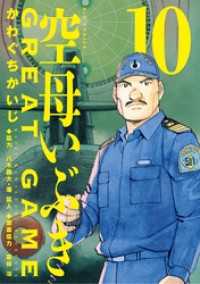
- 電子書籍
- 空母いぶきGREAT GAME(10)…
-
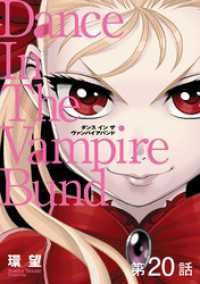
- 電子書籍
- 【単話版】愛蔵版 ダンス イン ザ ヴ…
-

- 電子書籍
- アラビアの花嫁【分冊】 10巻 ハーレ…
-
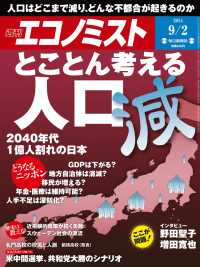
- 電子書籍
- 週刊エコノミスト2014年9/2号




