- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
格差の問題を前にして、我々はいったい何を求めているのか。人々を選別する〈能力〉とは何か──。学校は格差再生産装置であり、遺伝・環境論争の正体は階級闘争だ。だが、メリトクラシーの欺瞞を暴いても格差問題は解けない。格差は絶対になくならないだけでなく、減れば減るほど人間を苦しめる。平等とは何か。平等は近代の袋小路を隠すために我々の目を引きつける囮であり、擬似問題にすぎない。世に流布する議論の誤解を撃ち、真の問いを突きつける、著者最後の虚構論。
目次
はじめに──的外れの格差批判
序章 格差の何が問題なのか
能力という虚構
近代が仕掛ける囮おとり
格差がなくならない理由
規範論は雨乞いの踊り
私論のアプローチ
本書の構成
第1章 学校制度の隠された機能
学歴と社会階層
平等主義の欺瞞
支配の巧妙な罠
メリトクラシーと自己責任論
諦めさせる仕組み
日本の負け組
第2章 遺伝・環境論争の正体
ブルジョワジー台頭と進化論
知能テスト産業の発展
学問とイデオロギー
人種神話
相関関係の
遺伝と先天性の違い
遺伝論と新自由主義
第3章 行動遺伝学の実像
知能指数の矛盾
養子研究
双子研究
双子の個性
加齢による遺伝率上昇
遺伝率上昇の真相
遺伝率の誤解
第4章 平等の蜃気楼
擬制と虚構
主権という外部
個人主義と全体主義の共謀
裁判の原理
主権のアポリア
選挙制度と階級闘争
見えざる手
解の存在しない問い
異端者の役割
正義という名の全体主義
第5章 格差の存在理由
フランスの暴動
革命の起爆装置
比較・嫉妬・怒り
平等のジレンマ
近親憎悪と差別
第6章 人の絆
個人と社会の関係
贈与の矛盾
臓器国有化の目的
人肉食と近親相姦
同一化と集団責任
ユダヤ人という虚構
ユダヤの運命
同一性の謎
死者との絆
第7章 主体という虚構
内因幻想
意志と行為の疑似因果
意志の捏造
非決定論の誤解
両立論の詭弁
原因究明と責任のパラドクス
自由意志の歴史背景
神の擬態
自由意志という政治装置
犯罪とスケープゴート
処罰と格差の論理構造
終章 偶然が運ぶ希望
偶然の突破口
から出た実まこと
偶然と必然の密約
価値の生成メカニズム
信頼の賭け
偶然が紡ぐ未来
あとがき
引用文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
アナクマ
アナクマ
チャーリブ
アナクマ
-

- 電子書籍
- ワスレナグサ ~ミズキとけいこの物語~…
-
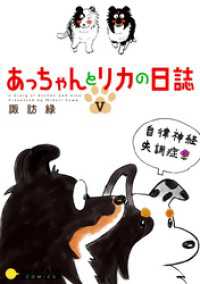
- 電子書籍
- あっちゃんとリカの日誌(5) コンパス…
-
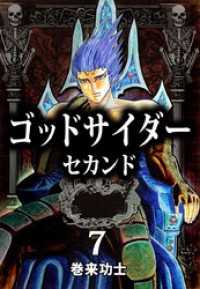
- 電子書籍
- ゴッドサイダー セカンド 7 まんがフ…
-

- 電子書籍
- ラクうま! 自家製お漬け物
-
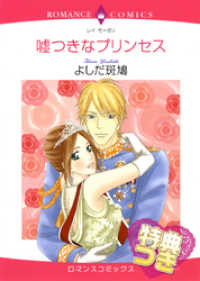
- 電子書籍
- 嘘つきなプリンセス【特典付き】




