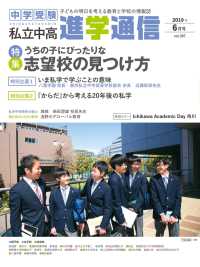- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「家」も「墓」も代々続いていくという考え方は
幻想でしかなかった
墓守が消失する「無縁墓」社会にあって
私たちはいかに死者を葬ればいいのか
地方の過疎化と高齢化は、
「増えすぎた墓」を世話する墓守の不足を急速に招いている。
満足に世話のできない遠方の墓を持て余し、墓じまいを行う人も増えてきた。
なぜ私たちはこれほどまで、お墓の存在を「重い」と感じるのだろうか。
墓じまいの実際とともに、
日本人にとっての墓の歴史、先祖供養のあり方、死生観の変化などにふれながら、
私たちが墓に執着する理由を解き明かしていく。
また、墓じまいにまつわる「寂しさ」や「迷い」、「わずらわしさ」の淵源に迫り、
「墓」から自由になるヒントを提示。
今後、「無縁墓」が増えていく時代の、新たな墓のあり方を考察する。
(目次)
第1章 私の体験した墓じまい
・墓守が不足した社会で、墓じまいは誰もが直面する問題・・・など
第2章 墓じまいにまつわるわずらわしさと解放感
・そもそも「家」というものは永くは続かない
・檀家制度がもたらす菩提寺とのトラブル・・・など
第3章 どうすれば墓じまいはできるのか
・日本社会で増え続ける無縁墓と改葬
・墓じまいの手続き、進め方・・・など
第4章 現在のような「墓」に長い歴史はない
・都市周辺の山に葬った平安時代の埋葬地の光景
・火葬の普及が庶民の墓造り、墓参りの習俗を生んだ・・・など
第5章 「故郷・実家・墓」の文化はほんの一時代のものだった
・誰もが墓をもつようになったのは最近のことである
・江戸時代から広まった寺と檀家という関係・・・など
第6章 私たちがもつ残された骨へのこだわり
・仏教、キリスト教も「遺骨」によって大いに発展した
・庶民にとっての供養の場は、もともと墓ではなく仏壇だった・・・など
第7章 墓じまいへの「ためらい」はどこからくるか
・墓はただの石か、魂が宿っているのか
・墓じまいは故人の思いに背くことになるのか・・・など
第8章 私たちにとって墓がもつ意味は変わった
・死後の魂の行方に関心を示さなくなった現代人
・親族たちが唯一、一堂に集まれる場としての墓の価値・・・など
第9章 墓じまいで心の荷を下ろす
・墓造りより、墓じまいのほうが日本人の無常観にしっくりくる
・「家」というものの重さから自由になる・・・など
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こちょうのユメ
coldsurgeon
sazen
こたちゅう
Asakura Arata



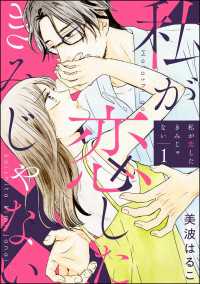
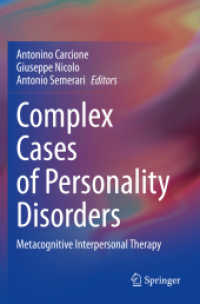
![good!アフタヌーン 2022年9号 [2022年8月5日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1258563.jpg)