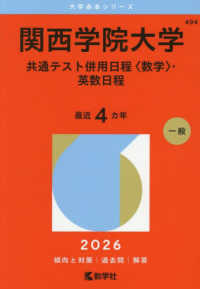内容説明
食育、伝統文化、地域活性化の視点から、今あらためて見直されている日本の伝統野菜。種類ごとに見やすく分類・配置し、子どもたちの調べ学習に使いやすい1冊です。
-
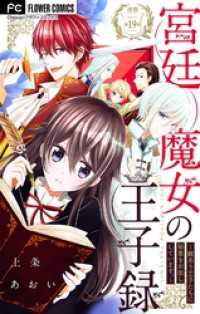
- 電子書籍
- 宮廷魔女の王子録【マイクロ】(19) …
-

- 電子書籍
- 真夏の千一夜【分冊】 12巻 ハーレク…
-

- 電子書籍
- 僕は小さな書店員。 6 マーガレットコ…
-
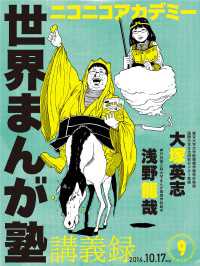
- 電子書籍
- ニコニコアカデミー 世界まんが塾講義録…