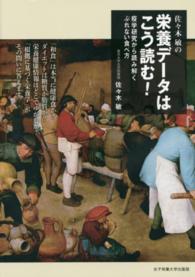内容説明
史学・考古学双方の研究を駆使して描く実態
ローマ帝国は衰亡したのか、独自の価値をもつ「古代末期」という新しいポジティヴな時代と捉えなおすべきなのか。本書は長年のこの議論をわかりやすく解説しつつ、「ゲルマン民族が侵入してきたとき、経済や社会に何が起き、人びとの暮らしはどう変化したのか」を、文献史料や陶器・家畜の骨・建築物(の跡)などを使い、史学・考古学双方の研究を駆使して描き出している。
ローマ帝国はさまざまな方法で経済的発展を促進し、税収による莫大な金銭を再分配した。ライン川とドナウ川に沿って駐屯していた職業的な軍が五世紀に崩壊すると、給料を得ていた何万もの兵士たちの購買力も失われ、彼らの装備を製作していたイタリア北部の工場も姿を消した。また皇帝たちは自身のために、交易を円滑にするインフラを維持したが、実際には貨幣は徴税官よりも商人や一般市民の手に渡るほうがはるかに多く、道路を旅するのも、軍より荷馬車と駄獣のほうがずっと頻繁だった。帝国の終焉とともに、これらへの設備投資は劇的に減少した。結果、地域の農業・工業の専門分化や作物・工芸品の換金が困難になると、住民はより生産性の低いシステムへの回帰を強いられ、人口は減少していく。
ローマ帝国の洗練された生産・流通システムがひとたび崩壊してしまうと、地域によっては先史時代の水準にまで後退し、回復には数世紀を要したという事実は、かなり衝撃的である。英国ペンクラブのヘッセル=ティルトマン歴史賞受賞。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Homo Rudolfensis
27
☆4.4 野蛮なゲルマン人の襲来と暗黒の中世→さほど蛮族的ではないゲルマン人とローマ人の融合による、ローマ文化の「変容」→著者の、古代末期にローマ帝国に起きたことは、紛れもなく「衰退」だ、とする考え。こうした、ローマ研究史の流れが本書の背景にあります。ゲルマン人進出の平和的側面を強調する考えを否定した上で、蛮族との不快な衝突と帝国の衰退を論じているため、暗黒の中世的な古い考えより、洗練されていてとても面白いです。2022/05/23
ゲオルギオ・ハーン
24
『ローマ帝国の崩壊』と聞くと、高校の世界史の教科書にあるような「蛮族」の侵入による崩壊、文明の壁が野蛮な力で崩されたというイメージがある。しかし、本書(というかローマ史研究の最前線)ではそうした単純な構図を否定する。なぜ、ゲルマン民族が帝国西方の地方でそれぞれ支配力を発揮したか。帝国の経済や軍事、行政が機能しなくなっており、強力な軍事力を持ったゲルマンなどの諸民族が地方の有力者と結びついて新しい社会づくりをしていくことになった。確かに識字率も下がり、経済も縮小したが決してネガティブな流れではなかった。2021/04/21
ようはん
22
西ローマ帝国の崩壊による古代から中世への転換は色々な解釈があるようだが、全盛期には現代でいう工場において高品質に大量生産され庶民にも行き渡っていた陶器が蛮族の侵入を経た帝国崩壊後には限られた富裕層にしか行き渡らなくなり庶民は低品質の自作の陶器を使用する等明らかに文明レベルが低下していた事が出土品から考察され、末期の蛮族侵入のダメージの影響を伺わせている。古代ローマ末期から崩壊の話を見るたび日本や世界情勢の現状を思い起こし、何となく古代ローマ末期の状態に陥っているのではないかと不安になる。2021/06/22
どみとる
13
ゲルマン民族の侵入によりローマ帝国は衰退したのではなく、一定の共生関係の中でキリスト教に裏打ちされた精神的な発展を遂げたー。著者は80年代に現れたこんな衰退否定論から戦後ドイツの国際復帰に連動した政治の匂いを感じ取る。ローマ帝国の崩壊により間違いなく洗練された快適な文明は失われ、先史時代まで後退した経済水準はその後千年間戻らなかった。誰にとっても経験したくない不快な侵略であり損失であったという事実を正しく認識すべきなのだ。今の快適な生活が続くと信じて疑わないのは、なにも古代ローマ人だけではないのだから。2021/03/09
akiakki
10
ローマ帝国は蛮族の侵入で崩壊したんじゃなくて緩やかに変質したと学説が変わったけどやっぱり崩壊だったんじゃねという本。東西分裂後、西ローマはポストアポカリプスを迎えたが、東ローマは割と繫栄してた。これが世相や時代に影響された結果、ドイツが悪者の時代はゲルマン民族が崩壊させた西ローマを、ドイツがEUに重要になると東ローマをローマ帝国全体に当てはめるように学説が変化したというのは妙に納得感があった。また経済や多様性文化で見れば崩壊であり、キリスト教世界で見れば変化となるように、視点の違いともいえる。2023/05/22
-

- 電子書籍
- みいちゃんと山田さん 分冊版(23)
-
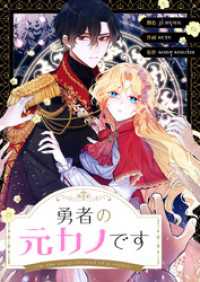
- 電子書籍
- 勇者の元カノです【タテヨミ】第91話 …
-
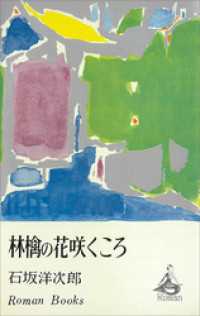
- 電子書籍
- 林檎の花咲くころ ROMANBOOKS
-

- 電子書籍
- 晴れのちシンデレラ (10) バンブー…