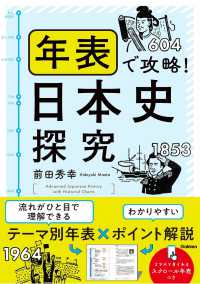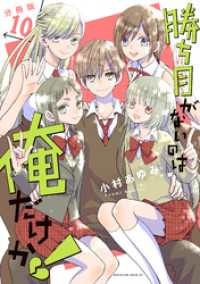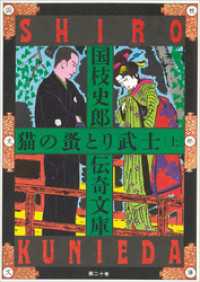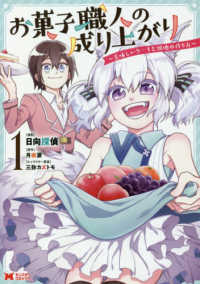内容説明
例題を多く用意し,自分の手で問題を解くことにより,理解を深め,知識を十分定着させることを狙った。例題等には公的資格である,公害防止管理者試験の類似問題を選び,環境法規関連を重視し,資格試験に対応できるようにした。
目次
1. 地球環境の危機
1.1 人口増加
1.2 密度効果
1.3 化石燃料の使用
1.4 地球環境の危機
演習問題
2. 地球温暖化
2.1 地球温暖化とは
2.2 地球温暖化のメカニズムとその原因
2.3 地球温暖化による影響
2.4 二酸化炭素の排出量
2.5 地球温暖化防止対策
演習問題
3. オゾン層破壊
3.1 オゾン層の概要
3.2 オゾン層の破壊物質
3.3 オゾン層破壊のメカニズム
3.4 紫外線の有害性
3.5 モントリオール議定書とオゾン層保護法
3.6 ドブソン単位
演習問題
4. 酸性雨および硫黄酸化物,窒素酸化物
4.1 酸性雨
4.1.1 酸性雨の発生機構
4.1.2 酸性雨の状況
4.1.3 酸性雨の影響
4.1.4 酸性雨への対応
4.2 硫黄酸化物
4.3 窒素酸化物
演習問題
5. 光化学オキシダントとPM2.5
5.1 光化学オキシダントとは
5.2 光化学オキシダントの環境影響
5.3 光化学オキシダントの現状と対策
5.4 浮遊粒子状物質およびPM2.5とは
5.5 PM2.5の環境影響
5.6 浮遊粒子状物質およびPM2.5の現状と対策
演習問題
コラム 環境思想家,芭蕉と賢治
6. 森林減少と都市緑化
6.1 森林減少の進行
6.2 森林減少の影響
6.3 森林減少の原因
6.4 森林減少対策
6.5 日本の森林環境
6.6 森林の世界遺産登録
6.7 都市緑化
演習問題
7. 放射線と環境
7.1 放射線の種類
7.2 放射線の性質
7.3 放射線の生物への影響
7.4 放射線のモニタリング
演習問題
8. 騒音,振動と環境
8.1 騒音と振動の概要
8.2 音と振動の性質
8.3 音の範囲
8.4 騒音と振動の測定
演習問題
9. 水質汚濁と環境
9.1 水質汚濁の歴史的背景
9.2 水質汚濁の指標と原因物質
9.3 環境基準と排水基準
演習問題
10. 水の浄化と水資源
10.1 水の性質
10.2 世界と日本の水資源
10.3 水質と生活排水
10.4 水の浄化
演習問題
11. 土壌・地下水の汚染
11.1 土壌の分類
11.2 植物にとって良好な土壌
11.3 土壌汚染の現状
11.4 農地の土壌汚染
11.5 市街地の土壌汚染
11.6 土壌汚染対策
11.7 地下水汚染の現状
11.8 汚染の仕組み
演習問題
12. 有害有毒物質
12.1 有害有毒物質と生体
12.2 人に対する毒性の種類
12.3 有害金属の毒性
12.3.1 カドミウム(cadmium:Cd)
12.3.2 水銀(mercury:hg)
12.3.3 鉛(lead:Pb)
12.3.4 ヒ素(arsenic:As)
12.3.5 クロム(chromium:Cr)
12.4 有機化学物質の毒性
12.4.1 有機リン系農薬
12.4.2 有機塩素系農薬
12.4.3 ポストハーベスト農薬
12.5 ダイオキシン類
12.6 自然毒
12.6.1 カビ毒
12.6.2 動物性毒
12.6.3 植物性毒
12.7 食中毒細菌
演習問題
13. 内分泌撹乱物質(環境ホルモン)
13.1 野生動物への影響
13.2 人への影響
13.3 内分泌撹乱化学物質の種類
13.4 ホルモンの作用と働き
13.5 懸念されている生体への影響
13.6 内分泌撹乱物質に対する国内外の対応
演習問題
14. 環境保全への取組み
14.1 環境行政と対策
14.2 環境基本法
14.3 環境アセスメント
14.4 化学物質対策
14.4.1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
14.4.2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法(化管法))
14.5 REACH規則
14.6 環境マネジメントシステム
14.6.1 ISO14000シリーズ
14.6.2 エコアクション21
演習問題
15. 災害と環境
15.1 地震波とは
15.2 地震発生のメカニズム
15.3 地震の環境への影響
15.4 火山噴火の頻度と火山分布
15.5 火山噴火の環境影響
演習問題
引用・参考文献
演習問題解答
索引