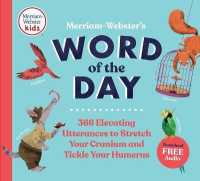- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「脳」「からだ(人体)」「ヒト」をめぐって「生きるとはどういうことか」を問い続けてきた解剖学者・養老孟司の代表的著作を読みなおし、その探求・思想の世界を一望する。「脳より大切なものがある」、「塀の上を歩け」、「あたりまえ」の本質、「無思想」という思想、「ヒトとはなにか?」……知的刺激に満ちた数々の至言とともに、東大医学部解剖学教室からの愛弟子である著者が、各著作が書かれた当時のエピソードも交え評伝風に語る。一冊でわかる、養老孟司のすべて!
目次
序章──一九八五年
脳より大切なものがある
最後の解剖学者
書き下ろしの著作を読み解いていく
第一章 『形を読む』──一九八六年
生物の形態を読み解く四つの視点
「数学的・機械的な見方」とは
「機能的な見方」とは
「発生的な見方」とは
「進化的」な見方とは
「重複と多様性」とは
相同と相似
自己と対象
「形態の意味」とは
見方を統一する
第二章 『唯脳論』──一九八九年
『唯脳論』を連載していた頃
現代は、要するに脳の時代だ
ヒトの脳の特徴は「交換」である
お金と言語は、同じもの
運動系が「目的」を生んだ
意識とは「脳を知る脳」のこと
心と脳と体の関係
死体とは、都市に残された最後の自然である
第三章 『解剖学教室へようこそ』──一九九三年
解剖学教室へようこそ
そもそも解剖とは
解剖には何カ月という長い時間がかかる
解剖に使う死体は、どこから来るのか
誰が解剖を始めたのか
人間と機械は、どこが違うのか
第四章 『考えるヒト』──一九九六年
「塀の上を歩け」とは
脳が脳をわかるか?
「脳と心は違う」のか
入力から出力へ
脳への情報入力
脳からの情報出力は「筋肉」のみ
世界像を構築する
意識について考える
「無意識」とはどういうものか
「たまには人間の自然を考えなさい」
口笛吹いて去る姿
第五章 『バカの壁』──二〇〇三年
本を書くことの「一種の実験」
われわれは自分の脳に入ることしか理解できない
「共通了解」と「強制了解」
個性が大切だというのは話がおかしい
「知る」と「死ぬ」
「情報は変わらない」とは
ピカソは、どのように天才か
利口とバカは少数派
お金の話は、脳の話である
「私の考えは、二元論に集約されます」
「自分の壁」を超える
第六章 『無思想の発見』──二〇〇五年
そもそも「自分」なんてものはない
だれが「自分」を作るのか
「世界中どこに行っても通用し、百年経っても通用する」もの
「私の心」とは、私だけのものなのか
「思想なんてない」という思想
般若心経とつながる
二人の解剖学者、三木成夫と養老孟司
第七章 『遺言。』──二〇一七年
自発的「書き下ろし」本
絶対音感
感覚所与とは
養老式二元論の図式
「イコール」があるか、ないか
民主主義と脳
時間の中での「同じ」
不死へのあこがれ
デジタルは死なない
ヒトはなぜアートを求めるのか
終章──二〇二〇年
養老孟司の著作一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
keroppi
tamami
三井剛一
ハチ
-
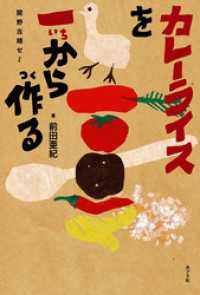
- 電子書籍
- カレーライスを一から作る ポプラ社ノン…
-
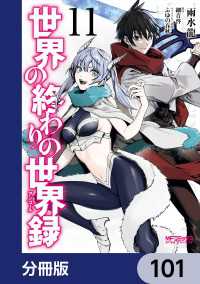
- 電子書籍
- 世界の終わりの世界録【分冊版】 101…
-

- 電子書籍
- 黄色い悪夢 リイドカフェコミックス
-

- 電子書籍
- 魔百合の恐怖報告コレクション 2 霊道…