内容説明
日本文化の核を育み、社会の階層をかき回した、渾沌と沸騰の200年! 豊かな乱世の絢爛たる文化――
日本の歴史の中でも室町時代の200年ほど、混乱の極みを見せた時代はなかった。が、一方では、その「豊かな乱世」は、生け花、茶の湯、連歌、水墨画、能・狂言、作庭など、今日の日本文化の核をなす偉大な趣味が創造された時代でもあり、まさに日本のルネサンスというべき様相を呈していた。史上に際立つ輝かしい乱世を、足利尊氏や織田信長らの多彩な人物像を活写しつつ、独自の視点で鮮やかに照射する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fseigojp
16
やっぱり南北朝になってからは複雑怪奇2015/08/04
目黒乱
15
仏像がつくられた当時の姿をCGで再現。よくこんな企画がありますが、それは極彩色や金ぴかの派手派手で、まったくありがたみがありません。緑青をふいたり、半ば朽ちかけているようなもののほうがいいのです。この書を読んで、このセンスが村田珠光のいう「幽玄の美」にあてはまるのではないかと思いました。煌々たる満月よりも、雲がかかった月のほうがよいという幽玄。室町時代は、日本文化の半ば以上を創造した時代だそうです。自分の美的センスのルーツが室町時代にあるかもしれない。そんなルーツ探しの気持ちでこの書を読むのも一興です。2015/10/16
satoshi
6
室町時代っておもしろい。天皇家が存続の危機にさらされたり、将軍が暗殺されたり、積極的に海外貿易が行われたり、トピックはいろいろあるのに、現在はどこか平安・鎌倉と戦国・江戸の「谷間の時代」みたいな扱いをされているのはなぜなんだろう。こうなったのは戦後だろうか。2011/06/01
げんがっきそ
3
室町時代で能、生け花、茶の湯、連歌、水墨画、作庭など日本文化の核となる趣味が創造されたらしい。これらは「人との交渉の場、もてなしの空間、サロン」として始まった。足利将軍の武力が覚束なかったため、公家や天皇の力を巧みに取り込むことで、権力を「もてなしや芸術」によって維持しようとした外交的な時代。サロンは外交的であるはずだが、これらの日本文化は時を経るにしたがい、内的な方面へ洗練された。日本人は内的に抑制された精神に一目をおく性質があるため、たとえ内的であっても、外交的な機能を果たせたのではないか?2021/03/05
ふら〜
2
室町時代の文化興隆を中心に書き上げてる本。やはり著者の山崎氏は読みやすい文章書くなと改めて思った。ついでに言えば日本史の授業を思い出して懐かしい気持ちにもなったり。2015/01/18
-
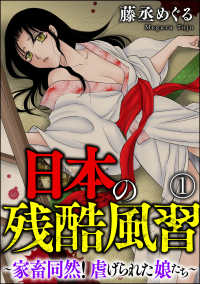
- 電子書籍
- 日本の残酷風習 ~家畜同然! 虐げられ…
-

- 電子書籍
- ご飯つくりすぎ子と完食系男子 (9) …
-
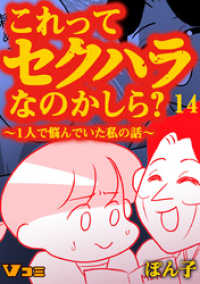
- 電子書籍
- これってセクハラなのかしら? ~1人で…
-
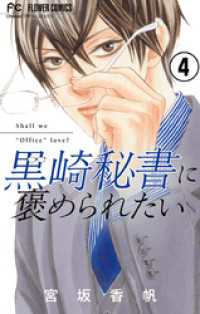
- 電子書籍
- 黒崎秘書に褒められたい【マイクロ】(4…
-
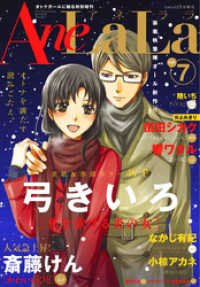
- 電子書籍
- AneLaLa Vol.7 AneLa…




