内容説明
青年は「世界最高にして最強の故郷アメリカ」をなぜ捨てたのか? ロシア語を学びソ連、東欧を経て、日本に辿りつき、ついには国籍を捨てオーストラリア人になった作家の回顧録・エッセイ。ホロコーストから逃げ延びたユダヤ人を祖先にもつ自分のルーツ、ケネディ時代からトランプに至るアメリカの真実、白豪主義の色濃く残った70年代から現代にいたるオーストラリアとオーストラリア人、1960年代から現在まで、50年にわたる日本と日本人の姿などをテーマに、宮沢賢治、石川啄木への熱い情熱、そして、井上ひさし、アンジェイ・ワイダ、大島渚、坂本龍一らとのエピソードを交えながらダイナミックに描いていく。
目次
日本版のためのまえがき
第一章 グラスの縁に腰掛けているような人生
第二章 ぼくはアメリカ人をやめた
第三章 ぼくの中の日本人
第四章 対岸の火事
第五章 賢治の網
第六章 ぼくの中のアメリカ人
訳者あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
86
昔、パルバースさんが宮沢賢治のことを「宮ざわざわ賢治」と形容しておられるのを読んで面白いと思った。様々な擬態語を駆使する賢治の文章をユーモアあふれて解説するこの人は只者ではない。東欧、西欧、日本、オーストラリアを転々とする中で、ベトナム戦争に象徴されるアメリカの偽善に嫌気がさしてアメリカ国籍を放棄したパルバースさん。国籍ではなく、人間の本質と向き合おうとする姿勢が、宮沢賢治や石川啄木の研究に繋がる。小津安二郎、ベアテ・シロタ、大島渚、井上ひさし、米原万里…パルバースさんが心を寄せる人たちの物語も魅力的だ。2021/03/04
R
31
ユダヤ系アメリカ人の著者が、日本で仕事をしつつ、オーストラリアに国籍を取って今に至るという半生を振り返った本でした。ある種哲学思想書のような面もあり、アメリカという国、そして、東西冷戦の影響色濃い時代を過ごしたこと、自身のルーツとの邂逅なんかも交えて、一人の人間としてどう生きようかという日々を積み重ねた内容だったように思う。現状のアメリカもそうだが、日本についてもある種の危機感を覚えているという警鐘もならしつつ、宮沢賢治が大好きという本だった。2021/05/31
ykshzk(虎猫図案房)
19
宮沢賢治や石川啄木の英訳で知られる元米国人の筆者は、米国人特有の独善性への違和感、ベトナム戦争への反抗等々から、祖国を離れ来日。その後米国籍を捨て、現在はオーストラリア人として生きている。Youtubeでも幾つか講演が聞けるが、もう日本人より日本人と言わせて頂きたい。自分は、自分が日本人として生きているという事について、真剣に考えてみたことがあるだろうか。「対岸の火事」というのは現代の世界には無い。皆同じ岸で生きているのだから。つまり、世界で起きることは繋がっているのだから。という内容が印象に残る。2022/11/08
マイケル
12
外側から見えてくるアメリカや日本、豪州。スパイ疑惑かけられ徴兵でベトナム戦争に行かされる前にアメリカ人をやめ日本とオーストラリアで暮らす。米軍に化学兵器使用されたベトナム戦争の戦争犯罪。広島と長崎はホロコースト。アボリジニの苦難。アメリカ人特有の自分だけが正しいという独善性。地下鉄サリン事件や東日本大震災時に日本にいた著者。著者を魅了する宮沢賢治の世界。「戦場のメリークリスマス」の裏話。根拠のない謝罪をする組織ぐるみの無責任、忖度の国日本。ソ連軍によるカティンの森虐殺など、歴史の勉強にもなる興味深い本。2021/03/18
Hiro
5
本書は十分共感できる誠実な本であるが、通読して私には何かまだ食い足りないところが残る。書名にある、米国人をやめた理由を、もっと詳しく赤裸々に語ってほしかった。割とあっさりとドライに触れられて、あとはもっぱら東欧や日本やオーストラリアでの異文化体験や様々な文化人との交流に多くのページが割かれている。これが対立と格差が増す不寛容な昨今の社会状況を憂うるエッセイ集ならともかく、私はコスモポリタンな著者の人生がどうやって形作られたのかを本質的に理解したかったのだ。なぜほかでもない日本に惹かれたのかも含めて。2023/03/05
-

- 電子書籍
- 【単話版】本好きの下剋上~司書になるた…
-

- 電子書籍
- 奈落の花 分冊版 39 マーガレットコ…
-
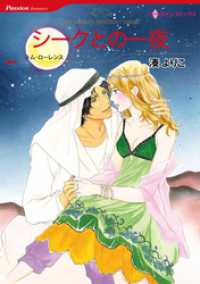
- 電子書籍
- シークとの一夜【分冊】 11巻 ハーレ…
-
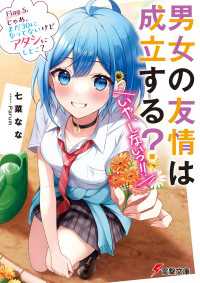
- 電子書籍
- 男女の友情は成立する?(いや、しないっ…
-
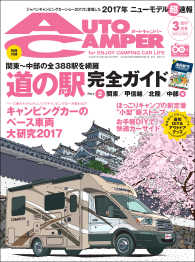
- 電子書籍
- AutoCamper 2017年 3月号




