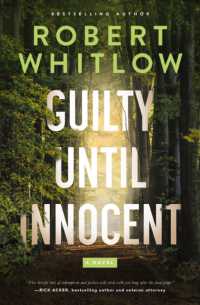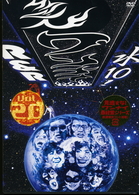- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
中国の都市部の世帯は、持ち家を平均1.5軒持っており、北京市の平均世帯資産は1億3392万円に上る。なぜ、彼らは「お金持ち」になったのか? 本書では急激に豊かになった(たとえば上海市の大卒初任給は30年前の190倍)中国人の資産の増やし方や消費傾向を紹介し、彼らのライフスタイルや価値観の変化を浮き彫りにする。 ●「Z世代」といわれる若者は従来の中国人とは異なり、商品の箱の中身を確かめないでモノを買う ●若者が憧れるKOL(キー・オピニオン・リーダー)――「ライブ・コマース」で商品を巧みに紹介する人たち ●ホワイトカラーよりブルーカラーのほうが可処分所得が多い ●農村住民や都市の非就労者が加入する年金の受給額は、月平均125元(約1875円) ●介護に関しては在宅介護が全体の9割を占めており、「子どもが老親の介護を負担するのは当たり前」という従来の考え方は今でも根強い ●コロナ禍の武漢での食生活は……
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
29
中国の消費実態の今(2020年刊)をリポート。「まったく新しい価値観を持つ」Z 世代(今の20代くらい)辺りが興味深い。95年生まれ前後の彼らは(お金を)「借りてでも使う」、90年生まれは「貯めない」、85年生まれは「貯めている」のだそうだ。日本の消費スタイルを追随しているような状態なのかな?とは言え、中国の若年層(10代後半~20代前半)失業率が20%弱という報道もあるので、中国の「明」の部分のスポットとして読むべき書かも知れない。不動産不況とも言われる今、御多分にもれず貧富の差は強烈なのだろう。2025/10/01
清游@草ぶえの丘で森林浴♨︎
25
『KOL』『完美日記』 『「閑魚」(Idle Fish)』『大衆点評』 若者世代だけで、日本の国家予算の約半分をグルングルン回す。借金してまでもグルングルン回す(金融リテラシーの基本思考が違うんだな)。 物理的な数値で、グングンと先へ行ってしまう。変化のギャップがあり過ぎて、例えば、数年前に深圳滞在して薬学勉強をされた方のお話を聞いた時があるが、どこの国の話をしているのか?さっぱりわからないほど(販売商品、インフラが激変している)。2021/11/20
mazda
13
中国の博士卒業者は、日本の学卒と同程度の初任給をもらっているそうなので、日本企業が中国で生産を行っていくことにメリットはなくなってきていると思います。1979年以降の一人っ子政策のため、今の40代の人たちは、子供の教育に莫大な資金を使うと同時に、親の介護もあり二重苦でアップアップのようです。これまでは住宅を買って転売というのが当たり前だったようですが、あまりにも高くなりすぎて購入を諦める世代も多いようで、住宅はもういらない、というトレンドになりつつある模様。2022/11/19
Hatann
9
著者は1988年に北京留学して以来、中国の市井に目を向けている。中西部の大都市にも目配りがあり、インタビュー人選にバランスが取れているところが心地よい。近年の著作は中国人の意識の定点観測のような意味合いがあり貴重だ。劇的な経済環境の変化が若者の消費・収入傾向の素早い変化を齎している。格差が広がり、学歴競争も激化する一方で、不動産所有志向が薄らいだ。著者が警鐘を鳴らす通り、中国については日本メディアの画一的な報道から受ける影響が大きく、根本的に見方を変えないと見る目がますます曇って現実とかけ離れるだろう。2021/07/22
ののまる
7
数年で様変わりする発展スピード。もうワシなんぞ、完全に浦島たろこ。2021/03/26
-
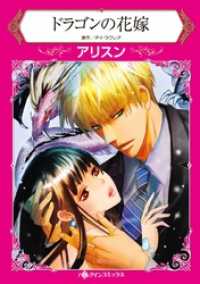
- 電子書籍
- ドラゴンの花嫁【分冊】 5巻 ハーレク…
-
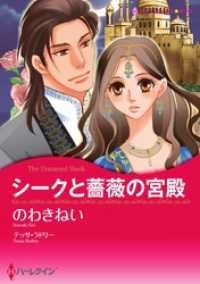
- 電子書籍
- シークと薔薇の宮殿〈【スピンオフ】サク…