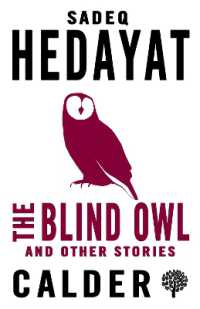- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「エゾに渡らんとせし頃より、新国を開き候ハ積年の思ひ一世の思ひ出に候間、何卒一人でなりともやり付申べくと存居申候」(慶応3[1867]年3月6日、印藤聿あて)――坂本龍馬 幕末と北海道。これら2つのキーワードで連想する志士は榎本武揚と土方歳三だろう。しかしここに1人、死の直前までひそかに北をめざした男がいた。あの坂本龍馬である。たんなる商売目的ではない。開拓移民。そこには新しい国づくりをにらんだ、深謀なるプランが隠されていた。蝦夷を探査した北添佶磨と同志・望月亀弥太の池田屋での死。海の男・浦田軍次郎と二度の海難。アイヌ語を勉強していたお龍。遺志を継いだ二人の甥・直と直寛――龍馬の壮大な志に、多くの仲間たちが夢を重ねていく。はたして龍馬が思い描いた国づくりとは何だったのか? 「排除しない生き方」とは? 大河ドラマではついぞ語られることがなかった、従来とはまったく異なる幕末史と龍馬伝。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
橋本環奈そっくりおじさん・寺
55
坂本龍馬は蝦夷地に行った事はない。しかし龍馬は北海道と大いに縁がある。だから函館に北海道坂本龍馬記念館が建てられた。その御縁の何たるかを書いた本である。蝦夷地の開拓は西洋からの脅威が深刻化した頃からの日本人の願いだった。龍馬もその一人に過ぎないのであるが、実践家である龍馬は具体的に活動してはその都度挫折していた。思えば龍馬という人はああ見えて、願い事の大半は叶わなかった人生なのである。本書は推測や引用が多く、水増し感も強いのだが、初めて知る話(お龍の再婚騒動等)もあって、著者が勉強家なのがよく伝わる1冊。2017/10/31
maito/まいと
4
龍馬と幕末と北海道にフォーカスした1冊。アイヌ語を勉強していたお龍や、蝦夷地(北海道)での展開を本気で目指していた龍馬など、新規資料が多く読んでておもしろかった。ただ、龍馬は現代で言うところのアイディアマン・プロデューサーで、晩年様々な事業拡大を行っていたことが知られており、蝦夷地は、その構想の内の一つと見るのが(全体像から見た)よりフィットした見方だろうと思うんですけどね・・・坂本家の継承者達が蝦夷地に移住していたとは知りませんでした(驚)2010/12/11
kou
2
周知の事実も蝦夷という視点に絞って編纂したことで新しい発見もあって面白い。反面、蝦夷に関しての言動のみを偏って取り上げたり、文献による確証も無いまま「ひょっとしたらあるかも」という可能性でしかない仮定を根拠に積み上げて論を展開しているため、蝦夷が龍馬の究極の目標のような書き方になっているところにムリを感じる。ドラマの脚本にしたら面白いだろうが。ただ坂本家・高松家は養子縁組がよく行われ家系図が複雑だが、そのあたりをスッキリと説明しているのは素晴らしい。龍馬が榎本を説得できたらというifにもロマンを感じる。2011/02/27
MIT
2
北海道の昆布が沖縄に運ばれていたことは知っていたが、薩摩藩が関与していたことは知らなかった。2011/02/19
-
- 洋書
- Éléments …
-
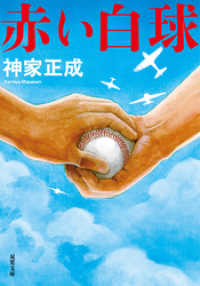
- 電子書籍
- 赤い白球 双葉文庫