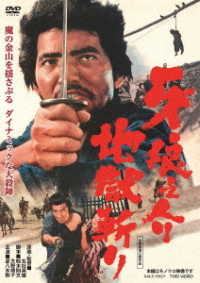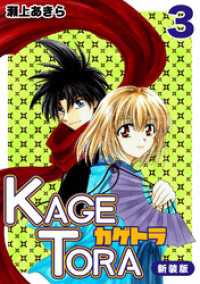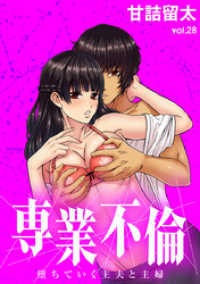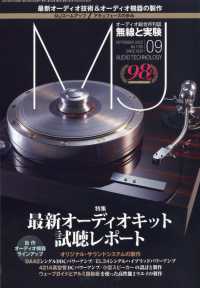内容説明
進化はなぜ、社会を生んだのか?
生物学の世界的権威の思想をコンパクトに凝縮した1冊!
仲間を作り、分業し、時に誰かを思いやる私たちの「社会」の起源は、狩りバチやアリなど、
人類が生まれるはるか昔から存在していた「真社会性」を持つ生物たちの、進化の過程が教えてくれる。
社会性を持つ生物は多く存在する一方で、高度な社会性(真社会性)を持つ種が進化史上、ほとんど存在してこなかったのはなぜか。
生物が社会をつくる条件としての、利他主義や分業といった行動はいかなる要因によって生まれるのか?
人類の進化を他生物の進化と比較しながら明らかにする社会生物学の創始者であり、ピューリッツァー賞など数々の輝かしい受賞歴を誇る世界的権威が、いま最も伝えたい人類進化のエッセンス。
吉川浩満氏による解説も収載。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
79
世界的な生物学の大家による集大成的考察。薄い本だがとても刺激的な書。なぜヒトは社会性を得たのか?5億年前に陸に生物が上がり今まで社会性を持つ生物はわずか2%のみ。4億年近く大型動物は100万年程の寿命で1000種以上存在したが、ヒトレベルの知性と社会組織に到達したのはヒト1種類のみ。今からわずか30-20万年前である。人類の進化のキーポイントは300-200万年前ホモ・ハビリス。雷による火災で動物の肉を食すようになり、火の使用と肉食で真社会性の先触れと分業を生み出した。脳の容量がホモ・ハビリス500cc→2020/09/26
うえぽん
46
社会生物学の巨匠が、自然科学と人文科学を融合させて、人間とアリ等の社会的行動に関する長年の考察をコンパクトにまとめた著作。生命の発生から言語の発生までの進化過程の全てがヒトの身体の中に痕跡があるとし、一つ上の段階に行く困難な過程の中に個々の細胞小器官や個体が全体に資するような働きをする利他主義が必要だとする。ただ、アリやヒトのように繁殖能力に劣る個体(働きアリや高齢女性)を含む協力分業という「真社会性」を有する種は希少で、種の発展に不可欠なのかどうか。論争的なテーマと分析だが、示唆に富むことは間違いない。2024/04/08
りょうみや
21
主に著者の専門である蟻や蜂の社会性昆虫と比較しながら、人間の利他心、他人を思いやる本能の起源を探っている。結局は個人で生きるよりも集団で生きるほうが生き延びる可能性がはるかに高く、長い間そうしてきたからということになるだろうか。あとがきの解説にもあるように人をシロアリなどと同じ真社会性生物(繁殖と労働が完全に分離)とみなすのは無理があると思える。美しい表紙で分量も少なく読みやすそうだが、内容はなかなか骨がある。2020/10/30
幸猪
18
利他主義に基づく動物の真社会性を解明することで、「私たちは何者なのか」「何が私たちを創り出したのか」「私たちは最終的に何になりたいのか」の問いに答えることができる。真社会性を発生させ高度な社会形態を持つ代表的な系統は、シロアリ、アリ、ハチ、そしてヒトである。ヒトをアリやハチと同じ真社会性を持つ系統と考える著者の論説は かなり無理があるが、ワーカーの利益(個人利益)かコロニーの利益(社会利益)かという線引きで考えると、思わず上記のことが解明されるのでは無いかと、期待を持ってしまいそうだ。2021/03/23
にゃんにゃんこ
9
動物や昆虫の社会性をDNAや進化から読み解く。面白さ352021/12/25