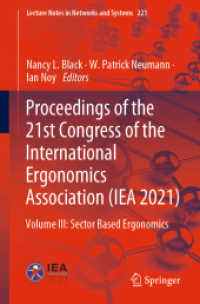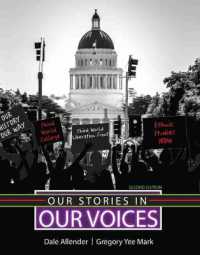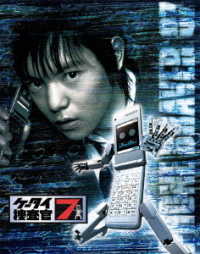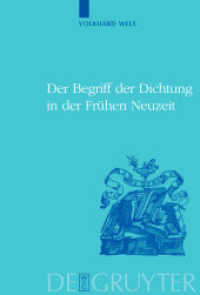内容説明
年齢を重ねたダンサーを起用したピナ・バウシュやジャドソン教会派、100歳を超えても踊り続けた大野一雄、老いを成熟とみなす能や踊りの分析をとおし、長時間労働と規律化が可能であるがゆえに近代で理想とされた「若い」身体の価値を再考、脱主体、脱近代的な身体の可能性を探る。
目次
はじめに
序章 老いのパフォーマティヴィティ──老いる踊り手、老いない踊り[中島那奈子]
はじめに
一 技術的な転回──生政治と老い
二 美学的転回──老いの美学
三 芸術的転回──老いと踊りの文化横断的研究
第I部 踊りの遺産
第1章 制作と稽古と継承のはざま──ピナ・バウシュの《春の祭典》が遺したもの[ガブリエレ・ブラントシュテッター](古後奈緒子・針貝真理子訳)
はじめに
一 《春の祭典リハーサル》──市田京美とのバウシュのリハーサルについて
二 《春の供犠》 ──コンテクストと伝達の作法
おわりに
第2章 老いと舞踊の哲学──絶対的他者としての老者の舞[貫成人]
はじめに
一 老いの実相
二 老いをめぐる歴史の諸層
三 老いの哲学
四 老いと舞踊──弱さを逆手にとること
第3章 ダンスにおける痛みの身体[イヴォンヌ・レイナー](外山紀久子訳)
はじめに
一 私の場合
二 老いていくパフォーマーたちとどう創作するか?
おわりに
第4章 コンテンポラリーダンス、長寿、人生の意味[ラムゼイ・バート](越智雄磨訳)
はじめに
一 老いをめぐる様々な言説
二 消費主義と老い
三 老いとダンス・パフォーマンスのポテンシャル
四 カウンターカルチャーとダンス
五 新自由主義時代の抵抗の場としてのダンス
おわりに
第II部 伝統での老いとポスト・ジェネレーション
第5章 上演の考古学──メレディス・モンクの《少女教育再訪》とレノーラ・シャンペーン作、出演によるソロ・パフォーマンス作品《メモリーの物置》[レノーラ・シャンペーン](常田景子訳)
はじめに
一 メレディス・モンクの《少女教育》を再訪する
《メモリーの物置》シノプシス(二〇一四年)
《メモリーの物置》(二〇一四年、東京での上演のためのソロ・パフォーマンス台本)
第6章 論説と鼎談──日本舞踊と老い
一 老いと舞踊[渡辺保]
二 老いる未来と若返る伝統[花柳寿南海×花柳大日翠×渡辺保]
三 解題[中島那奈子]
第7章 日本における「老い」と「踊り」[尼ヶ崎彬]
はじめに──二つの問題
一 「老い」とは何か
二 「衰退」としての老い
三 「年功」としての老い
四 「余生」としての老い
五 老いた身体──大野一雄の場合
おわりに──展望
第III部 グローバル化する老いのダンスドラマトゥルギー
第8章 老女と少女の物語[やなぎみわ](文責・中島那奈子)
はじめに──美術と演劇の並走
一 「マイ・グランドマザーズ」
二 「グランドドーターズ」
三 「フェアリーテール」
四 「ウィンドスウェプト・ウィメン・シリーズ」
五 《関寺小町》の舞踊について
六 日本の老女の表象
七 《日輪の翼》
第9章 日本の神話と儀礼における翁童身体と舞踊[鎌田東二]
はじめに──談山神社「談山能」(二〇一四年五月一三日開催)における《翁》と「摩多羅神面」から
一 老いの神性としての「翁」神──『八幡愚童訓』の事例
二 日本の神話と儀礼における「老い」と「若」の表象──霊性の軸としての「翁童」表象~稲荷神・猿田彦神・八幡神
ほか