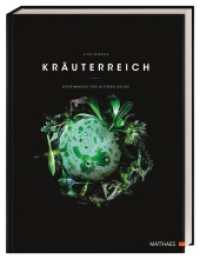内容説明
1800年、アンリ・ベール(ことスタンダール)はナポレオン戦争に従軍し、後年このときの記憶を書きとどめた。第一次世界大戦が間近い、不穏の気配ただよう1913年には、ウィーンからヴェローナ、リーヴァに向かったドクター・K(ことカフカ)が日記をのこした。1980年、カフカの足跡を追って同じ旅をした語り手の〈私〉は、死と暴力の予感におののいてヴェローナから逃げ帰った。その7年後、当時の記憶を書き記そうとかつての道をたどり直し、最後に自分が捨てた故郷に立ち寄った。
〈私〉の旅、カフカの旅、スタンダールの旅―時を超えて重なり合う旅のどこにも、永遠の漂泊者「狩人グラフス」が影を落とす。さまざまなものや人が響き合い、時間と場所を越えて併存する。本書はゼーバルト初の散文作品であり、「ベール あるいは愛の面妖なことども」「異郷へ」「ドクター・Kのリーヴァ湯治旅」「帰郷」の4篇を収録。
「たえず動いている乗り物のなかの想念に似て、消えては結び、やってきてもつれ合い、断続して定めがたい。つまりはもっとも現代的な散文表現というものだ」。池内紀氏による巻末の解説「言葉の織物」から引用。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
風に吹かれて
25
1800年のナポレオンによるアルプス峠越えの列に属していたアンリ・ベール(調べてみたらスタンダールのことだった)のこと、1980年の「いつにもまして厭な時を、場所を変えることによって何とかやり過ごせないか」とヴェローナを旅したときの『異郷へ』、1933年にウィーン、ヴェローナなどを旅したドクター・K(カフカのこと)のこと、1987年に訪れた故郷W村へ行ったときの『帰郷』、四つの散文で構成された一冊。 →2022/06/01
三柴ゆよし
18
四つの物語を収録。どの作品にもカフカの、特に「狩人グラフス」の影が落ちている。ほかにもカフカでは、「審判」や「変身」を髣髴させるイメージもあり、作中、語り手がいみじくも語っているように、一種、推理小説的な謎解きゲームとしても楽しく、ゾクゾクさせられる。私は所々カフカの日記と手紙を参照しながら読んだが、ゼーバルトの企図が過去の探求とその踏み外し(重点は主に後者に置かれている)にある以上、極力、じぶんもその過程に同化しつつ読むといいだろう。ゼーバルトの作品では、歩くこと以上に、偏執的な読み替えが行われている。2020/08/24
ケイトKATE
18
ゼーバルト初の散文作品である本書は、スタンダールとカフカが訪れた場所を辿って行く話と、著者自身が幼少期を過ごしたチロル地方の村を訪れた話で構成されている。本書にはすでに、ゼーバルトの散文作品に登場する文章に合わせた写真と、語り手である私と登場人物の語りが溶け込む文章が出てくるが、傑作である『アウステルリッツ』や『移民たち』に比べ、読み手を引き込ませる文章が少なく物足りなかったのが正直な感想である。2020/07/02
Bartleby
13
本書もまた旅について。今回は、スタンダールのした旅、ドクター・K、つまりカフカの旅。そこへ、著者が幼年期を過ごしたチロル地方への旅が重なる。でも相変わらず一筋縄ではいかない。例えば美とグロテスクさがないまぜになった独特の描写を読んでいて、じつはそれがカフカの短編からの引用だったと気づかされたりする。下手したらすべてが引用による織物なのではないかという気さえしてくる。そして現実もまたこの小説と同じだなと繰り返し思った。けっきょく何を信じ、何を信じないか、その塩梅だけが、現実を成り立たせているのかも。2023/01/04
バナナフィッシュ。
4
普通故郷の思い出といえば、懐かしく温かくそして成長した自分から見ると僅かな疎外感を感じるものだ。この小説は違い。暗い村落に降りたちもういなくなった人達や、消えてしまった建物を憶い出す。それは感慨という感情とは程遠く、絶望とも違う、孤絶した何かだ。2020/07/20