内容説明
日本人はくり返し流行する疫病を神として祀ることで、その災厄から逃れようとしてきた。都の発展は病の流行を生み、疫病退散のために祇園祀りが行われた。また、ある種の疫病は「怨霊」として人々から恐れられてきた――。そこには、一神教の世界と異なり、多神教の日本だからこその疫神を祀るという行為がある。長い歴史の中で、日本人はどのように病と闘ってきたのだろうか。
【目次】
第1章 医学はどれだけ流行病に無力だったのか
第2章 疫病神としての天照大神
第3章 疫病は仏教伝来のせいなのか
第4章 天然痘の大流行が東大寺の大仏を生んだ
第5章 祗園祭の起源は疫病退散
第6章 菅原道真を怨霊とした咳病はインフルエンザ
第7章 疫病がくり返される末法の世が鎌倉新仏教を生んだ
第8章 なぜキリスト教の宣教師は日本に疫病をもたらさなかったのか
第9章 虎狼狸という妖怪の正体はコレラ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田中峰和
5
歴史を振り返ると、宗教は疫病の流行と密接な関係があることがわかる。神代に遡ると天照大神は疫病神として恐れられていた。天皇の近くではなく伊勢神宮に祀ったのは感染を恐れたから。明治天皇まで代々の天皇は伊勢神宮に参拝さえしていない。20年ごとの式年遷宮も、よほど疫病の祟りを恐れていたからに他ならない。次に仏教伝来と疫病との関係。欽明天皇が金ぴかの仏像に感銘を受け仏教を受け入れたが、やがて疫病を流行らせた元凶とされ廃仏になった。その後逆転し、疫病を退散させると信じられた。科学が進歩する前は宗教しかなかったのだ。2020/12/19
ユウユウ
2
★32024/05/24
わ!
2
なるほど、こんな宗教史の読み解き方もあるのか…と、とても面白く読めた。コロナ禍だから「疫病VS神」というタイトルであるが、もう少し範囲を広げて「災厄VS神」としても、ほぼ同じ様な内容になっただろう。つまり宗教には、蔑ろにしたタイミングで災厄が発生したために現在でも存続しているものや、崇められたタイミングでたまたま災厄が下火になっが故に現在でも存在しているものがある。さすがにそれだけの理由で現在まで存続している宗教などはほとんどないのだろうが、これらの事象が奇跡として語り継がれているケースも多いのだろう。2023/08/30
philosophia1976
0
宗教学者・島田裕巳氏による日本の宗教史と疫病についての新書。医学の進展で感染症の原因がすぐに特定できる現代では、新型コロナウィルス禍に宗教の出番はなかった。しかし原因を特定することのできなかった時代には、疫病は神の怒りであり誰かの祟りであった。無力であるがゆえに為政者や民衆は祈り、償い、鎮め、治めようとした。そのように「得体の知れない何か」に理由をつけることで疫病を乗り越えようと試みたのである。もしそのタイミングで疫病が蔓延した(しなかった)ら歴史は変わっていたかもしれないという著者の考察は興味深かった。2023/06/21
むむむ
0
ほとんどの感染症とは共生の道をとらざるをえない。その方途を示唆してくれる一冊。一神教では、神があらゆるものを創造するため、出所不明のウイルスとの相性が悪いとの指摘に納得させられた。一方で、日本など多神教においてはその限りではない。 また、江戸時代にコロリを図示したり、アマビエを描いたりして目に見えぬ存在を具現化することで、得たいの知れぬものに対する恐怖を解消するというのにも納得できる。2020/10/21
-
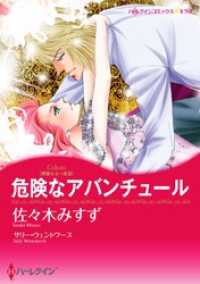
- 電子書籍
- 危険なアバンチュール〈華麗なる一族II…




