内容説明
大震災の現場から政府の教育政策を問い直す!
東日本大震災は、とくに岩手・宮城・福島の三県に未曾有の事態をもたらしました。被害からの「復旧」「復興」が急がれています。特に、子どもと教育の問題については、先送りにできない緊急の課題です。
本書は、長年、教育現場での実践について研究してきた第一線の教育学者が、現場の声をふまえて、今何をなすべきか、これからどう進めていくべきなのかを提言するものです。
現場のことを知らない「お上」からの画一的な指示では、「想定外」の事態に対応できないのは、原発事故の対応と同じだと言えるでしょう。大震災は、効率やコストを重視し過ぎることの問題を浮き彫りにしました。今後の復興においては、多様性や分権を大切にしなければなりません。教育についても同様です。管理強化と効率第一主義の「改革」によって、先生が子どもと向き合う時間がなくなった現状を改め、教育を子どもと先生のもとへ取り戻すことの大切さを訴えます。
目次
第1章 三月一一日の子どもたち
第2章 大震災後の先生と子どもたち
第3章 原発事故に振り回される子どもたち
第4章 これからの学校はどうあるべきか
第5章 政府の震災対応と教育政策への提言
第6章 被災地の復興から学校教育の再生へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ねええちゃんvol.2
3
★★ 福島の4年生のセリフ「福嶋氏ってこんなに放射能が高いのに、避難区域にならないのはおかしい。福島や郡山を避難区域にしたら、新幹線や高速を止めなくちゃいけなくて、そうすると経済が回らなくなるからでしょ。俺達は経済活動の犠牲になって、見殺しにされるってことだ。」 タイトルの学校の大問題についてはよくわからなかったです。2011/10/12
Riopapa
2
東日本大震災によって日本の様々な問題点が明らかにされたが、教育政策、教育行政のあり方もその一つ。筆者も指摘しているが、教員は忙しすぎて、国の教育政策をじっくり研究したり、批判する時間もない。福島の先生方は本当に大変だと思う。国の言うこと対し疑問を持ちながら、大丈夫と言い続けなければならないのは、戦時中と変わらないのかもしれない。2011/09/23
にゃみ
1
東北の田舎の狭い港町で、地域の結びつきが比較的まだ高い地域だから、これだけ逆に生存できた人がいたのかなと。避難所の話なんか、もし東京や大阪とかの都会でこういうことになったら、子供たち同士は一緒に遊んだり結びつきは強いだろうけど、都会の核家族ばっかりで親同士の結びつきがないからあれだけうまく回らないだろうし、結果助かりそうな命がどんどん助からない結果に終わってしまう気がした。2011/12/26
時折
1
こういう考え方の人がいるのは知っているけど、でも、震災を、本を売るためのネタにしているようなこの本のつくりはいい感じがしない。こんな人が教育学者だったりするから、日本の教育はダメなんだ、きっと(すみません、責任転嫁ですか?!)。2011/10/10
よし
1
前半は、東日本大震災による被災地の学校現場の様子が検証されています。著者自らの現場調査は少なめに感じましたが、様々な新聞記事や公表資料を基に丁寧にまとめられていると思いました。後段は、あるべき教育について述べられていますが、その多くは「震災前から求めてきたこと」のように思われ、若干違和感を感じました。2011/08/30
-
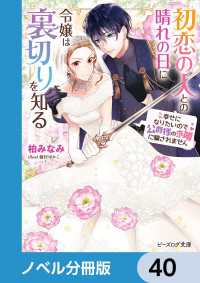
- 電子書籍
- 初恋の人との晴れの日に令嬢は裏切りを知…
-
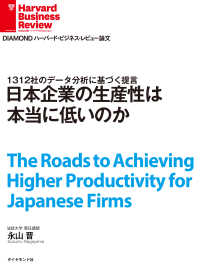
- 電子書籍
- 日本企業の生産性は本当に低いのか DI…
-
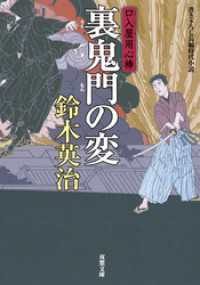
- 電子書籍
- 口入屋用心棒 : 16 裏鬼門の変 双…
-
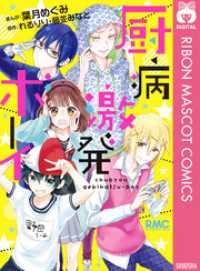
- 電子書籍
- 厨病激発ボーイ りぼんマスコットコミッ…
-
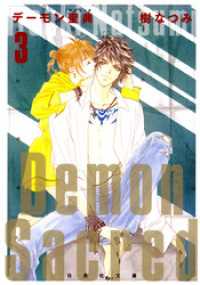
- 電子書籍
- デーモン聖典(サクリード) 3巻 白泉…




