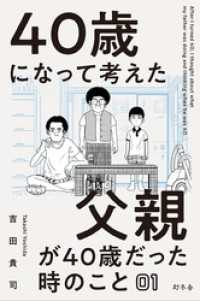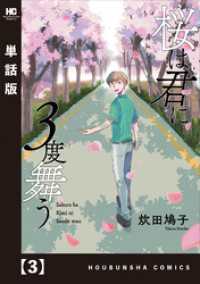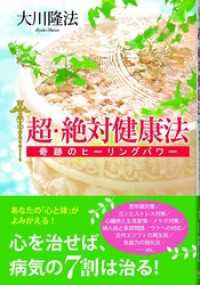内容説明
あらゆる知的創造は、“準備”“培養”“発現”“検証”という四つのプロセスを踏むことで生み出される。では、人間がもつ思考の可能性を最大限活用し、「ひらめき」を意識的に生み出すような方法とはどのようなものか――。バーナード・ショーらとともにフェビアン協会の中心人物であったイギリスの政治学者・社会学者グレアム・ウォーラス(1858‐1932)。彼は、混迷を深める危機の時代にあって「思考」がなによりも重視されるべきと考え、そのメカニズムを原理的に究明しようとした。ジェームス・ヤング『アイデアのつくり方』の源泉ともされる創造的思考の先駆的名著、待望の邦訳。
目次
はしがき
凡例
第1章 心理学と思考
思考が必要とされる時代
思考プロセスの探究
機械論的理解
ホルメ的理解
協調と統合
第2章 意識と意志
意識とは何か
意志とは何か
身体と精神
第3章 技法に先立つ思考
思考を観察できるか
記憶による観察
同時的な観察
ヴァーレンドンクの解釈
ポアンカレの解釈
第4章 コントロールの諸段階
思考プロセスの四段階
〈準備〉段階と〈検証〉段階
〈培養〉段階
〈培養〉を妨げるもの
〈発現〉段階
ひらめきの〈予兆〉
〈予兆〉を妨げるもの
第5章 思考と情動
〈予兆〉を色づけるもの
ユーモアという情動
情動の役割
理性と想像力
第6章 思考と習慣
習慣という刺激
辺縁の思考の記録
アイデアを膨らませる
習慣の主人たれ
第7章 努力とエネルギー
思考と努力
習慣とエネルギー
情動の機能
行動とは何か
二つのエネルギー
第8章 思考のタイプ
人間集団による類型化
英国的思考とフランス的思考
政治的思考における相違
アメリカの「開拓者精神」
アメリカの創造的エネルギー
第9章 意識の遊離
催眠状態と思考
確信の感覚
意志によるコントロール
自己暗示と瞑想
第10章 教育の技法
現代のプラトンたち
子どもまかせの弊害
心的エネルギーを刺激する
余暇の必要性
新たな試み
心理学的視点の導入
第11章 公的教育
義務教育の役割
高知能の子どもたちへの有効手段
中等教育の義務化
第12章 教えと実践
教員登録制度の弊害
思考の技法の伝達と実践
柔軟な教育制度
学校の役割
実験学校の可能性と限界
原註
解説(平石耕)
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
iwtn_
polythenepam_m
K.Miyahara
☆ツイテル☆
jiroukaja