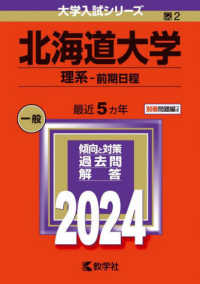- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
近現代の仏教は、つねに最先端の科学と接点をもち、自らの可能性を問い直し続けてきた。宗教体験の心理学、禅や祈祷の科学的解明、さらには催眠術、念写、透視の研究まで。ときに対立し、ときに補い合う仏教と科学の歴史から、日本近代のいかなる姿が浮かび上がるのか。ニューサイエンス、オウム真理教事件、そしてマインドフルネスの世界的流行へ――。対立と共存のダイナミズムに貫かれた百年史を、気鋭の近代仏教研究者が描き出す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
73
キリスト教では進化論論争などがあるが、仏教と科学という取り合わせが新鮮で手にした一冊である。仏教の教義と科学との間の哲学的な論考を期待したが、心理学、催眠術、加持祈祷、坐禅、超能力、オカルトなど(それが科学?)と仏教との関係に多くの紙幅が割かれ、少し残念。そんな中で、鈴木大拙先生と湯浅泰雄先生の考察が心に残る。鈴木先生は、「概念」である科学に対して、仏教は「体験」を通じて主客合一を図ると言い、湯浅先生は、「修行」によって身心一如を実現するのだとする。そういう実践的アプローチが仏教の科学的側面かもしれない。2020/10/27
yutaro13
25
『仏像と日本人』を著した若き仏教研究者の新刊。科学と仏教というテーマで想起するの佐々木閑『科学するブッダ』の壮大な試みだが、本書が描くのは明治以降の仏教と科学との対立と共存のダイナミズム。明治期の心理学との関与、催眠術との接近、戦後の禅・祈祷の科学的分析、そしてニューサイエンスの流行とオウムの出現。「仏教の性質や瞑想の効能を科学的に検証し、それらを仏教の枠内から科学の領域へと移そうとする運動」が反復されてきたと著者は言う。マインドフルネスが流行する現代を相対化するために欠かせぬ歴史的視点を提供してくれる。2020/10/24
あしお
3
とても良い本だと思う。最近は禅宗の坊さんも脳波とか脳内ホルモンとかを持ち出して禅の素晴らしさが科学的に証明されたように言う人が多い。確かに絶対者を設定する一神教に比べて「法」や「縁」と言う超越者の恣意的な介入のない世界観を持つ仏教は科学と馴染みやすいのだろう。しかし、科学は客観的な真理であるのに対して宗教は主観的な真理である。「客観的に幸せな状態」が当人にとって幸せとは限らないように、科学が宗教を飲み込むことはないのだろう。2021/09/07
なをみん
2
「仏教には「心の科学」とも評せるような性格が、確実にある。」ってのは大前提として、心理学の始まりから催眠とか禅の科学の歴史とか鈴木大拙とか、ニューサイエンスとかとか、中沢新一とオウムと脳内革命からマインドフルネスまでいろんな話をちょっとずつ。この著者の×(かける)仏教的一連の著作は現代的でどれも見事に興味深い。座禅中の内臓の変化の科学とかちょっと気になる。2025/06/30
2n2n
2
心身の問題とは、科学と宗教の双方にまたがる領域なんだって話は、確かにそうだよなって思う。古くは催眠術、現代ではマインドフルネスに深く関わる話(´・ω・`) あと、米国のマインドフルネス・ブームとは瞑想の商品化による新たなマーケットの形成だって話は、いかにもアメリカって感じがした。つまりマインドフルネスとは、瞑想法を特定の宗教伝統から切り離すことで効率化したという一面があるという。言うなれば、瞑想のファーストフード化🍔ってところか(´・ω・`) 2024/04/13
-

- 電子書籍
- 最強医仙の都市修行記【タテヨミ】第94…
-
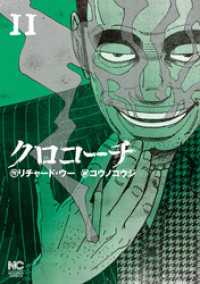
- 電子書籍
- クロコーチ 11