内容説明
心と脳は同じものなのか.心はすべて物理的な理論で説明がつくのか.心と脳はなぜ「サイクリングと自転車」の関係に似ているのか――.『世界はなぜ存在しないのか』で「世界」を論じた気鋭の哲学者がつぎに切り込むのは「心」.脳科学全盛の時代に,実存主義と心の哲学をつなげ,21世紀のための新たな存在テーゼを提示する.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
k5
78
やたら読みにくい本論と、それにまつわる四人の論考、さらに回答という複雑な構成ですが、対話形式になっていることでかろうじて全体像が見えます。しかし、哲学的な思考が得意でない自分にはあまり刺激的でなかったかな。たとえば、意識論としても傳田博士の『皮膚感覚と人間のこころ』の方が合います。「水にとってH2Oであることがそうであるように、ある対象の「本質」がそれを全面的に規定する内的性質のことだとすれば、そうした性質なるものは人間の生の理解を助けるカテゴリーではない」という第3章の記述がいちばん腹落ちしました。2020/07/23
けんとまん1007
66
いつ以来だろうか、これほど読むのに苦労する本は。哲学の素養が薄いこともあるだろうが、文章自体も難解なものがある。それでも、「心」というものについて関心が高いので、読むことができた。心と脳。心はどこにあるの?と聞かれると、心臓のあたりをさしてしまうのも何故だろう。脳の働きに過ぎないとは思えないというか、思いたくないというのがある。引き続き、読んでみたい著者だ。2020/04/16
1.3manen
52
新実存主義の考えでは、心は自然の秩序(宇宙)にも世界にも属さない。FOS(意味の場)の系列全体にまたがって存在する(19頁)。心と脳の条件モデル:心と脳の関係は、与えられた状況を複数の必要条件とそれを組み合わせた十分条件とに分析してはじめて浮かび上がってくる(76頁)。この分野に疎いせいか、理解は不十分であった。2020/07/25
きいち
44
心の存在をめぐる対話。『なぜ世界は存在しないのか』のガブリエルの小論に4人の哲学者が論及、それに対してのガブリエルによる再回答からなる。この本の構造、そして、この思考がどう自分につながるのかなかなか捕まえられなくて苦しむ。◇「人間のあり方は、自分自身をどうとらえるかに本質的に左右される。自分が描いた自画像を踏まえて人は行動するから」、そしてテイラーの「他者への貧弱な理解がどんな破局的事態をもたらしたか」という危機感から入るとよいのかな?◇でもなぜあえて「新」実存主義という名づけなのか?保留しつつ次いこう。2020/05/06
フム
34
芋づる式の読書をしないではいられないせいで、3冊目のマルクス・ガブリエルとなった。前に読んだ2冊に「新実存主義の考えによると…」という主張が繰り返しされていたので、ともかく読んでみたものの難解だった。全く理解した気がしないのに、どういうわけか心地よく読み続けることができてしまい、読み終わった。ガブリエルの新実存主義に対して、4人の研究者が論じ、さらにガブリエルが返答するという構成。難解ながらも、最後まで読むと、少しばかりわかる部分も出て来て、もう一度第1章を読み直してみた。2020/09/12
-

- 電子書籍
- 異世界コンビニのおっさん、実は最強。【…
-
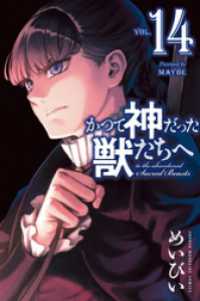
- 電子書籍
- かつて神だった獣たちへ(14)
-

- 電子書籍
- 舞子「ガールフレンド」SPA!グラビア…
-

- 電子書籍
- 園芸家12カ月 新装版 中公文庫
-

- 和書
- OD>忍術秘伝の書




