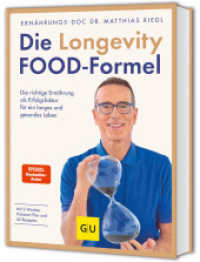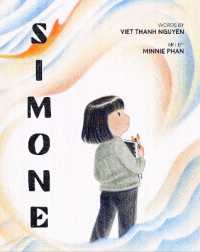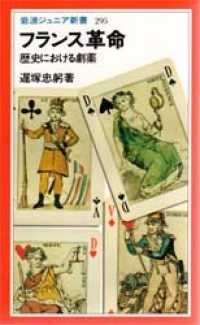- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
日本の農政が大転換期を迎えています。「プレーヤー」の育成を柱にすえ、農業法人が力をつけ、企業参入が軌道に乗り、農協改革も始まるなどの成果を収めていますが、それでも、農家人口と産出額の減少には歯止めがかからず、生産基盤の弱体化が深刻な問題となって日本の食料問題にのしかかっています。
なぜうまくいかなかったのか。背景にあるのは「農政のジレンマ」です。戦後農政は米国に配慮しながら、食生活の変化に対応して畜産と果樹を振興しました。指針となったのが、「戦後農政の憲法」の旧農業基本法です。しかし1980年代に牛肉・オレンジの自由化要求で基本法農政は否定され、90年代はウルグアイ・ラウンドで主食のコメも標的になってしまいました。苦境に対応し、農政は競争力強化に傾斜したが、「ブレーキとアクセルを同時に踏む」状態に陥り、今日にいたるのです。
そこで日本農業が目指すべきは、経営政策から食料政策への転換です。本書は、食料供給力を構成する「技術」「農地」「人」の3つの観点から、日本の農業が抱える課題と可能性を検証し、「過保護」と「自由競争」の狭間をぬうナローパスの道筋を明らかにすることで、未来への処方箋を探ります。
コンセプトは「逆転の発想」。技術に関しては、環境を高度に制御するスマートアグリを紹介する一方、日本の多くの農場は環境に大きく左右されるアナログ的な状況が将来にわたっても続くため、人の「習熟」に寄り添う形の技術開発が必要になります。
食料の供給基地である農地保全では、日本の土地利用型農業の代表である稲作を中心に分析。大規模経営が直面するハードルや、疲弊するブランド競争の実態などを伝えます。そのうえで、新たな農地利用の可能性として、田畑のサービス業的な利用の可能性についても論じます。
最後が「人」。これまでの常識を超えるグローバルな経営者が登場しています。だが実は、戦後の農地解放で生産者が経営感覚のない小規模農家に「解体」される前、日本の農業には経営があった。そして、未来の農業経営者の登場に道を開くためには、後継者を作ることのできなかった既存の農業には限界があり、市民農園などを通して「潜在的な競技人口」を増やすことが必要であることを訴えます。ここで、農地のサービス業的利用という「農地」の問題が、「人」の問題に結びつく。平均年齢が70歳に迫る状況を「危機的」と批判することが多いが、実は70歳になっても続けることができる農業は、日本の超高齢化社会の理想像であることも示されます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kan
Toru Fujitsuka
くらーく
お抹茶
mobius8