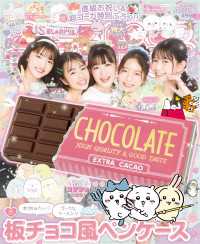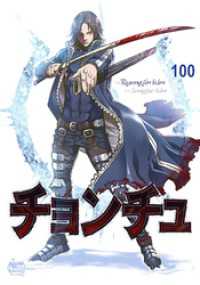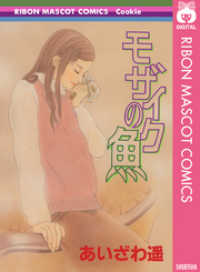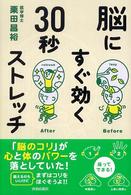内容説明
日本国憲法の制定過程を、ポツダム宣言受諾後の「ポツダム・プロセス」として見ることで憲法のほんとうの姿がわかる! 気鋭の国際政治学者による、世界水準の憲法入門講義。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
93
図書館本 はじめての憲法…、たしかに憲法をそこそこ学んだ人が初心にかえるという意味においてもはじめての憲法でした。 大まかにいうと日本国憲法の解釈の争点って大陸合理諭vsイギリス経験論+プラグマティズムの勢力争いの図式に落とし込めるのかなぁ。意外と私の場合は大陸合理諭に寄っていたということを再確認。英米方式では主権をことさら強調しないのだとか…。英米方式で書かれた日本国憲法をヨーロッパ式で読むからおかしなことになるのですね。2022/03/26
Francis
15
平和構築がご専門の国際法学者篠田英朗さんの新著。「ほんとうの憲法」で示された篠田さんの憲法論が大学での講義という形で分かりやすく示されている。日本国憲法は国際連合規約・パリ不戦条約の精神と条文を踏まえて制定されたこと、そしてポツダム宣言の受諾から日本国憲法制定の過程はボスニア・ヘルツェゴヴィナやカンボジアなどで行われた平和構築と同様のプロセスであり、ポツダム・プロセスとも言うべきものであることを論じている。篠田さんの日本国憲法についての考え方は一貫しており、とても優れていると思う。2020/04/21
まえぞう
13
著者は憲法学者ではなく国際政治学が専門のため、戦争・平和・憲法と言う観点をベースに議論が進みます。ポツダム宣言受諾からサンフランシスコ講和条約締結までをポツダム・プロセスととらえ、憲法前文と9条の話しが中心です。おおよそはそうだろうと思いますが、そこまで整然と整理できるのかなぁとは感じました。2020/01/04
mft
11
日本国憲法の成立過程から説き起こし、主な議論の対象である九条を前文とともにその起草者たる GHQ の意図(著者の了解としてはそれが正当解釈である)に従って解説する。憲法の理解にポツダム宣言が必要とはこの本を読むまで思っていなかったし、そういえばポツダム宣言を読んだこともない2020/01/18
kenitirokikuti
9
図書館にて。平和構築学(Peace-building studies)から日本国憲法の成立の流れを解く。憲法前文の第2段〈日本国民は[…]平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。〉これをドイツふうに読んではいけない。「平和を愛する諸国民」はGHQ草案では“the peace-loving peoples”。この言葉は太平洋憲章にも国連憲章にもあり、枢軸国の侵略を受けたために平和を希求する国々(の人たち)を指す。要するに第一義は単に国連加盟国でしかない。2023/09/19