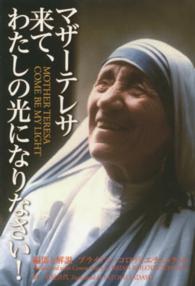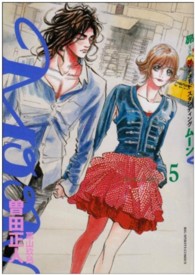- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
学習指導要領の改訂や大学入学共通テストへの記述問題・民間試験導入で大きく揺れ動く国語教育・英語教育。本書では、この危機の時代に、国語と英語という「ことばの教育」にはそもそもどんな意味があるのか、そしてどうやって「ことばの力」を鍛えるのかを、それぞれの分野の専門家三名がリレー形式で思考する。私たちの思考の根本をつくるのは「ことば」である。その教育が、子どもたちの未来をつくる。「ことばの教育」を考えることこそが、いま大切なのである。
-

- 和書
- なぜ?なに?めいず