内容説明
メディア・アートは、なぜそう呼ばれているのか?
ポストインターネット状況を経た、21世紀の芸術精神を探る!
現在、メディア・アートという名称は、単にメディア・テクノロジーを使用した美術作品の総称というだけにとどまらず、技術を応用したデモンストレーションなども含めて幅広く使用されています。
そしてメディア・アートは、「ポスト・インターネット・アート」やデジタル・ファブリケーション、デザイン、現代美術などさまざまな領域と接続しており、多くの人の関心を集めています。また、ライゾマティクスをはじめとしたテクノロジー×エンターテイメントの活動にも注目が集まっています。
しかし、メディア・アートを明確に定義することは難しく、メディア・アートをめぐる言説に関しても複数が錯綜している状態です。
本書は、最先端の工学に明るく、創作者としても活躍中の久保田晃弘さんと日本のメディア・アートのメッカ、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で20年間メディア・アートの現場に携わってきた畠中実さんという第一人者の二人が、メディア・アートに関する論点をわかりやすく整理・解説した入門書です。
メディア・アートの歴史や重要なキーワードを学ぶにはうってつけの一冊となっています。
芸術表現の可能性を切り開く、メディア・アートの世界へようこそ。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TOMYTOMY
3
限界まて来たアートに対して、ポストインターネットは何が出来るのか。 もはやガチャガチャやキーホルダー、商業施設のモニュメントにされるアート。 難しい用語もありながらこれからを考える示唆を含んでる。 二人も具体的に何か見つけようとしている感じもして、これをブレイクスルーどうされていくのか。2018/04/30
doji
1
久保田さんがしきりに分断について言及しているのが気になった。理系と文系、コードを書くものと書かないもの、といったものだけではなく、それはメディアという媒介するものについて語るからこそ感じてしまうつながりであって、それが現在どんどん失われてしまっているということなんだろうとおもう。つながりっぱなしなのはインターネットだけで、ひととひととは分断した時代だからこそ、メディア・アートのもつ意味は大きい。2019/11/07
さのかずや
1
メディア・アートを芸術、文化の系譜に照らして論じることを専門としている両名による、メディア・アートの定義、あるいは指針を導き出そうとする議論をまとめた本。中身について語るにはもう一回読み直さないといけないし、おそらくスライドが何枚も必要になるけど、今読めてよかった。来月「メディアアーツ・ミートアップ」なるものに登壇が決まっているが、どんな準備が必要か考えあぐねていて、まあそんなに準備なくてもいいかな、と思っていたが、ちゃんと話をしないといけないなと考え直した。最後まで、理性的に。最後まで、諦めずに。2019/09/29
わだ りゅうた
0
まさに「原論」だった。対談をまとめた書籍になっており、授業を読んでいる気分だった。 所々にキーワードの解説があるのがありがたい。 つい最近畠中さんのトークイベントに参加したが、問題意識などはこの書籍と全く変わっていないと感じた。つまりそこには今なお議論できるものが隠れているのである。 また、この書籍では脱人間中心主義が少し語られている。しかし今現在のAIは人間中心で動いているし、果たして脱人間中心主義になったテクノロジーが良いものなのかは今の社会から見ると疑問である。 2025/11/28
m
0
メディアアート作品は好きなのだがメディアアートがなんなのかはよくわかっていなかったのでこの本を読んでみたのだがあまり意味はなかった。この本に書いてあることは「メディアアートに明確な定義はない」ということとそれに続いて具体例を出していき、続いて自分のメディアアート作品の案を提示してるんだがその内容というのが「人類が滅んだ後も残る作品」として宇宙に作品を残すというもので、なに言ってんのこの人。観測者不在の作品にどれだけの意味があんの?ていうかそういうのが知りたくて読んだんじゃないんですけど。2021/02/05
-

- 電子書籍
- ど底辺令嬢に憑依した800年前の悪女は…
-

- 電子書籍
- 悪女ヒロインに転生~美男子も権力もお手…
-
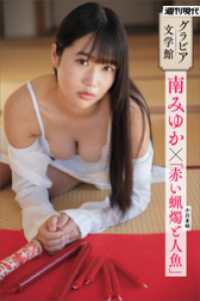
- 電子書籍
- 【グラビア文学館】南みゆか×小川未明「…
-

- 電子書籍
- 8月の光 SMART COMICS
-
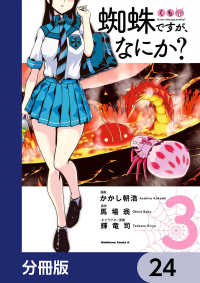
- 電子書籍
- 蜘蛛ですが、なにか?【分冊版】 24 …




