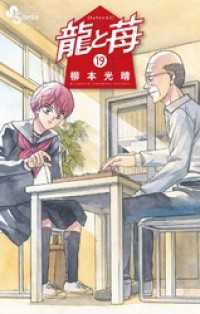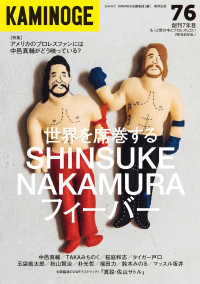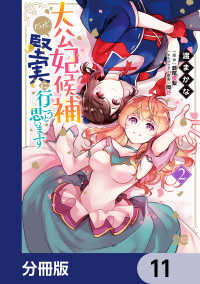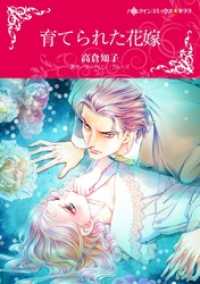内容説明
古代ローマでは、発掘されただけでも数万種類にのぼる貨幣が存在した。貨幣は一般に権力の象徴とされ政府や中央銀行などが造幣権を独占する。だが、ローマでは政界に登場したばかりの若手や地方の有力者も発行していた。神話の神々、カエサルや皇帝たちの肖像、ヤギや北斗七星など描かれた図像も多岐にわたるが、彼らは貨幣を用いて何をアピールしようとしたのか。図像と銘文から読み解く、新しい古代ローマ史入門。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
50
文句なくおもしろい。コインの図像や刻文から、これだけ多くの事柄を「解読」するには、よほどローマ帝国の歴史に通じていなければならないだろう。小さなコインが、政府のあり方や権威の諸事情まで、何と雄弁に歴史を裏付けて語ってくれることだろうか。ローマのコイン自体の当時の価値変動については、金属の品位を問題にしない計数貨幣であるためか、ほとんど述べられない。その点は、意外なほど近代的。2018/10/29
ゲオルギオ・ハーン
27
貨幣の図像を取り上げて古代ローマ史のことを書いた新書。流通量や金や銀の含有率の変化などの経済的な視点はなく、ローマ史の概要にしては帝政期に話が集中しているためバランスが悪い。あとがきで書いているとおり、自分で調べてみる取っ掛かり的な位置付けの本だと思いました。指摘として面白かったのは五賢帝期は血の繋がりがないように見えて、トラヤヌス帝の姉マルキアナを中心に見ていくと家系図的に繋がっていくことでした(さらに母親のマルキアで考えるとフラウィウス朝にも繋がる)。意外とローマ皇帝の血筋って繋がるみたい。2021/05/16
サアベドラ
26
共和制から帝政末期まで、貨幣の図像からローマとその属州の社会の変化を読み解く。2018年刊。著者の専門は共和制末期で、本書のテーマの貨幣学でも何本か論文を書いている。前近代の貨幣は文字通り当時の社会や経済を映し出す鏡であり、材質や図像など、様々な切り口で話を広げることができる、非常に魅力的な題材である。ただ、本書は決してつまらなくはないが、そのような貨幣学の面白さを十分に伝えきれていないように感じる。文章が少々ぎこちないのと、扱う範囲が広すぎて全体的に散漫な印象を受けるのが原因なのかもしれない。惜しい。2018/12/14
組織液
17
まぁ題名の通りの内容です。ローマの変遷と共に変化していった貨幣の刻印などに関して解説されています。正直自分も、クラウディウスの時は統一されたクラウディウスの刻印が入った貨幣が、ネロの時はネロの貨幣がバーっと発行されてるのかと思ってたんですけど、全然違いましたね() 皇帝はもちろん、共和制期には造幣三人委員、元老院などが自らをアピールする為に刻印を使ってたのは興味深かったし、今から見ると結構公私混同な国家のように感じました。非常に読みやすかったです。2020/09/04
中島直人
16
(図書館)貨幣の図像から、ローマの歴史を紡ぎ出す。それにしても、2,000種類も発見されているとは驚き。貨幣という他にはない切り口からの考察であり、興味深く面白く読めた。2018/12/01