内容説明
指揮棒を持つのと手で指揮をするのとではどう違うのか、ピアニスト出身とヴァイオリニスト出身、作曲家出身の指揮者では、どこが違うのか。そもそも指揮者によって、あるいは同じ指揮者でさえ演奏が変わるのはなぜなのか……。
著者はアメリカの指揮者・教育者で、「有名な大指揮者の伝記や指揮法の教本でないものを」という依頼に応えて、本書を執筆したという。その結果誕生したのは、指揮というアート・職業のあらゆる角度からの検証であり、ごくわずかな人間しか知らない世界や心理を垣間見せてくれる、ユニークな作品である。
どの章も、著名な音楽家との自身の経験もしくは、晩年のアシスタントや作品の初演を務めたレナード・バーンスタインからじかに聞いた貴重なエピソードをふんだんに盛り込み、とっつきやすく、飽きさせない。一方で、ベートーヴェンの有名な曲を例に、ある場面を自分はどう解釈し、オーケストラにどう表現させるためにどういう指示を出すかを説明したり、クリティカル・エディションの「正しさ」と批評家や聴衆の「常識・慣習」との折り合いの問題を解説するなど、ディープな音楽ファンにも楽しめる内容になっている。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
39
アマ演奏者である我々にとって、音楽を見事に整えてゆく指揮者は魔術師である。しかし、その仕事は「怪しげで混沌として」おり「ペテン師的ないかがわしさ」にも満ちている。現役指揮者による本著は、作曲家、独奏者、演出家、批評家など「さまざまな関係」に翻弄される指揮者の悲哀がよく描かれているが、私には、マーラーの交響曲第4番冒頭のフルートにnot rit.と書き込んだバーンスタインや、「春の祭典」の変拍子の小節線を手書きで動かしたクラウスの例のように、楽譜を通じて「指揮者は何を考えているか」をもっと教えてほしかった。2019/08/09
まるほ
34
かなりの読みごたえでしたが、とてもおもしろかったです。▼第1線の現場で活躍する指揮者による“指揮者”についてのあらゆる側面について書かれた本。ここまで当事者目線に沿った内容のものは実はあまりないので、とても興味深く読みました。▼指揮についての歴史、指揮のテクニック、スコアの読み方、指揮者になるための勉強法、演奏論、指揮者が対峙する様々な関係者との関係(演奏家、ソリスト、聴衆、評論家、マネジメント関係者)、指揮者の生活、など。▼結構ストレートに批判的に言及している箇所もあって、実に興味深かったです。2020/12/26
Fondsaule
27
★★★★☆ 「指揮者は何を考えているか」という題なので、解釈とか、テクニックとかも書かれている。 けれど、内容は色々な指揮者のこぼれ話的な話が結構多い。 バースタインとカラヤンのはなしとか・・・ 原題は「マエストロとその音楽 : 指揮の芸術と錬金術」 "Maestros and their music : The art and alchemy of conducting "2022/05/18
たまご
26
いやあ,面白かったです! 現役指揮者である筆者の辛口コメントも面白い! クラシックファンにはマストでは?! 指揮者のお仕事内容(読書,もっと言うと詩を読むのとすごく似てると感じ)+お仕事請負事情,オケやソリスト,歌手との関係はもちろん,誰がその仕事のボスなのか,というあたりも結構赤裸々にあかされてる,かなー? 録音と生演奏の違いを読んでいて,きっとポストコロナには,実体験は非常に価値のある,稀有な経験となってしまうのだろうなと思いました. 全てが一期一会になってくのだろうなと.2020/05/04
マカロニ マカロン
20
個人の感想です:A。表題通り指揮者がどんな仕事ぶりなのかが、ベテラン指揮者の著者だけでなく、バーンスタイン、ストコフスキー、トスカニーニ、カラヤンなどを例に挙げながら語られていく。特に興味深かったのは指揮の歴史、スコアの読み方、協奏曲でのソリストとの関係、長距離指揮者の孤独、録音対生演奏の章。『春の祭典』初演時のモントゥーと作曲者のやり取りは自分の好きな指揮者の話で新鮮だった。またバーンスタインとBBC交響楽団の攻防の話もとても面白かった。指揮者ならではの詳細なスコアの読み方もとても勉強になった。2020/02/03
-

- 洋書電子書籍
- オックスフォード版 音楽検閲ハンドブッ…
-
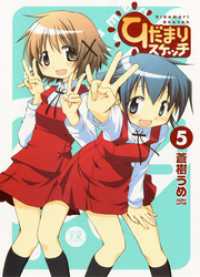
- 電子書籍
- ひだまりスケッチ 5巻 まんがタイムK…
-
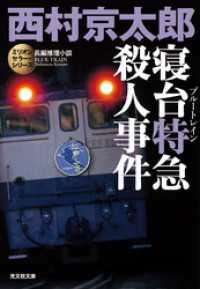
- 電子書籍
- 寝台特急殺人事件 - 長編推理小説
-
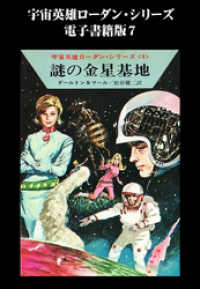
- 電子書籍
- 宇宙英雄ローダン・シリーズ 電子書籍版…





