- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
喉が渇いたときに飲む水は心底おいしいけれど、渇きがおさまった後に同じ水を飲んでも、もうおいしいとは感じない。体が必要としていないから。すなわち「おいしい」とは本来、体という自然によりそい喜ばせてあげたときに生まれる感覚のこと。しかし、ただおいしいだけでなく、この「体が喜ぶ料理」を作るのが案外難しいと著者は言う。どうしたらそんな料理が作れるのか、そもそも料理とは何か――。京都で最も予約が取りにくい日本料理店「草喰なかひがし」店主が、野山を馳せ巡りながら得た〝食〟にまつわる究極の哲学。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
95
京都・銀閣寺門前の小さなカウンターだけの店「草喰なかひがし」の店主。大原の地野菜を毎朝愛車の真っ赤なスズキX-90で仕入れに行く。畑から抜いたばかりの野菜をちぎって生で食べて、料理を発想する。草喰の草は、真行草の草の意味。真書が本膳料理だとしたら、草書の料理はそれを崩した草の料理。畑で出会う自然をまるごと味わってもらえるように仕掛けをする。人は食べることによって自然を感じて、季節を味わう。京都へ行く際には是非予約して味わいたい。https://www.soujiki-nakahigashi.co.jp/2022/04/30
Asakura Arata
5
食文化というのはこういうことなのだろうな。食材と会話するには、産地に直接行って五感を開いて触れるしかない。本当の料理人というのはそういうものだ。2019/10/24
niz001
5
仮に30年ぐらい前の著作と言われても驚かない、自然をなるべく自然な形でいただこう。結局昔も今も変わらないという事か。直接書いてはいないけど「殺生なことしはるんですなあ」と言った人にはムッとしたやろなぁ。大山椒魚のお造り!?もう食べられへんけど。2019/08/08
peko
3
とても読み応えのある本だった。一流の人、モノごとを突き詰めた人の話はおもしろい。大原も花脊も、京都市内だけれども自然にあふれ静かで大好きな場所だ。超有名店でなかなか行けない店だが、こういう店が人気があるというのが、まだまだ世の中捨てたものじゃないな、と偉そうにも思った。2019/12/27
Humbaba
2
物の価値というのは不変ではない。昔はそれほど価値が認められていなかったものも、時を経て希少性が増して誰もがうらやむようなものにと変わることもある。松茸もかつては簡単に手に入るものだったが、現代では貴重品になってしまった。貴重品ではいろいろと為うのも難しいが、そうではなかった時代には様々な食べ方を試して、失敗を重ねながらも新しい味を見つけることにも成功した。2024/03/22
-

- 電子書籍
- 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君【分…
-

- 電子書籍
- ポンコツお嬢様は悪魔と契る 2巻 FU…
-

- 電子書籍
- 探偵はもう、死んでいる。【ノベル分冊版…
-

- 電子書籍
- 仕事中毒な魔法公務員は少年勇者に慕われ…
-
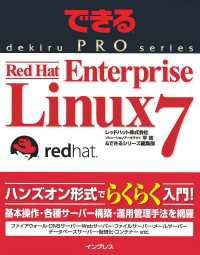
- 電子書籍
- できるPRO Red Hat Ente…




