内容説明
「そうだ。おれたちはこんな黄金ラーメンでぐんぐん育ってきたのだ!」(椎名誠さん推薦!)安くてボリュームたっぷりで昭和の胃袋を満たしてくれた町中華。特別な味でないのにクセになり、通いたくなる店、個性的な店主たち。中華なのになぜオムライスがあるのか。なぜ戦後に増え始め、なぜ常連客に愛されるのか。町中華探検隊・隊長であるブームの火付け役が、数百軒を訪ね歩いた経験から描ききる、町中華の来し方行く末。アメリカの小麦戦略や、化学調味料ブーム、つけ麺で人気の『大勝軒』の復刻メニューのエピソードなども交えて、昭和を生きた男たちなら誰もが持っている記憶の琴線に触れる。消えつつある食文化の魅力あふれる1冊!
目次
はじめに
第一章 町中華はどこからきたのか~もろびとこぞりて
第二章 町中華の黄金期~ワリバシは踊り、鍋は炎に包まれた
第三章 町中華よ何処へいく~太陽はまだ沈まない
おわりに
主な参考文献
掲載店情報
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
63
子供の頃は、町中華なんて言わなくてラーメン屋さんでした。おそば屋さんのカレーライスとかラーメン屋さんのカレーライスなんて言っていたように記憶しています。あの頃からおじさんは、そこでビールを飲んでいたし、私は、その横で炭水化物をたくさん摂取していたのです。いつか、チャーハンに餃子、焼きそばもシューマイだって一人で食べてやるんだ!熱くそう感じた日もありました。先日、学生さんがそんな食事をしてるのを見て、しっかり受け継がれているぞと胸が熱くなりました。2019/09/19
ホークス
49
2019年刊。次第に減りつつある町中華の歴史と魅力を追う。関東の取材がメインで、著者らしい情がよく出ている。戦前から東京人形町にあった『大勝軒本店』の流れや、荻窪『丸長』の流れ。『丸長のれん会』は今も続いているのが頼もしい。戦後期に多くの個人が開業して町中華は急増。求めに応じて丼物や洋食などを取り入れメニューを増やした。取材先の東府中『スンガリー飯店』には入った事がある。只者じゃない外観に反し、優しい町中華の味だった。荻窪『丸長』から独立したつけ麺の『東池袋大勝軒』も、最初のメニューは町中華そのもの。2022/06/12
竹園和明
40
以前読んだ『ドライブイン探訪』的。レストランともラーメン屋とも違う中華版大衆食堂を“町中華”と位置付け、日本を代表する町中華・大勝軒本店、下北沢丸長など店の歴史と町中華の歩みを綴る。その掘り下げ方が深く、結構マニアックだ。「町中華に求められる『旨い』は安定感と日常的な満足感」とは言い得て妙。また、町中華の強力打線、“3番:炒飯、4番:中華そば、5番:中華丼”というのもその存在感と役割を思えば納得。中華そばと炒飯があれば自分は大満足。カウンターの油で腕がくっついて剥がれないくらいの店があったら教えて(笑)。2019/08/10
ばんだねいっぺい
34
本書の題は、素晴らしいなぁ。まさか、町中華の裏にアメリカありとは、思わなんだ。化調のピリピリに、美味すぎない良さ、マンネリの心地よさ。 明日の夜は、雪駄でもはいて、やる気なくラーメンを食べよう。 2019/08/25
DEE
15
ランチに職場の近くで何となく入った中華料理屋が美味しかった。 自分は食べたい物が決めてから店を決めるのでその逆は珍しいのだけど、その時は他にピンとくる物がなかったのだろう。 いい店を見つけたと思っていたところに出会ったのがこの本で、そういう中華料理屋を町中華と呼ぶらしい。言い得て妙だと思う。 メニューを専門化することはせず、請われるがままメニューは増え、ズバ抜けた味より安定を目指す。だから飽きないし常連もつくのだろう。 ちなみにそこはよだれどり冷麺が美味しかった。町中華にしてはオシャレなのかも 笑2019/08/29
-
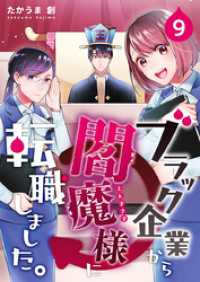
- 電子書籍
- ブラック企業から閻魔様に転職しました。…
-

- 電子書籍
- ファンタジー放送局36 ROCKETO…
-
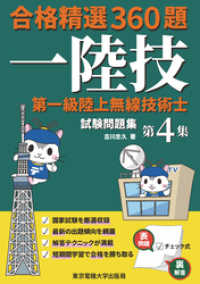
- 電子書籍
- 第一級陸上無線技術士試験問題集 第4集
-
![天堂家物語[1話売り] 第二十五話 花とゆめコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1054099.jpg)
- 電子書籍
- 天堂家物語[1話売り] 第二十五話 花…





