内容説明
「近代」とはいったい何だったのか? ラディカルに近代化を果たさねばならなかった日本では、その文化的側面の多くを「文学」が背負うことになった。役割を担わされた文学は「新しさ」を表出するために進出し続けた。その進化論的パラダイムにとりつかれた時代との格闘が「教養」の源泉となり、現在まで私たちの底流で生き続けている。テクスト分析を駆使し、日本近・現代の文化的慣習の形成過程をくっきりとあぶり出す斬新な論考。
目次
第1章 文学史と観察者
第2章 進化論の時代
第3章 なぜ主人公が必要なのか
第4章 物語と主人公の力学
第5章 固有名という装置
第6章 写真が与えた衝撃
第7章 表情を読む感性
第8章 苦悩を書く文体の誕生
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ロッキーのパパ
14
明治期の文学作品を題材に日本の近代を詳しく掘り下げている。同時期に掲載された夏目漱石と小杉天外の比較が興味深い。今売りだせば小杉天外の方がエンターテイメント小説として売れそうな気がする。それでも、漱石の方が残ったのは時代を超える価値があったってことか。2013/05/18
1.3manen
10
書名には関心があったものの、内容まではなかなか、門外漢の評者にはついていけなかった。岩井克人先生の貨幣論は少し理解できる(147頁)。この間、高校現代文に共通地の悲劇論も取り上げられてあったので。「命がけの飛躍」なんて概念は初めて知った。商品が貨幣体系に組み込まれることらしい。夏目漱石の色々な著作分析や、白樺派の検討は今後の課題にしたい。2013/06/21
ハチアカデミー
8
近代はおそらく、終わっていない。いまなお進化論的パラダイムの中に私たちはいる。その創世記に書かれた文学作品、主に漱石を俎上に、それらの成立史と広がっていく過程を追わんとした一冊。フーコーと絡めつつ、近代のまなざしを論考した「文学史と観察者」「写真が与えた衝撃」の二章が特におもしろい。自然主義文学・さらにはその先の私小説のテーゼともいえる「無理想無解決主義」の萌芽を、坪内逍遥『小説神髄』に見いだす指摘は至極鋭い。近代文学成立期のおもしろさを再確認。とはいえ、タイトルの「教養」はやや強引か。2014/04/11
mstr_kk
4
第一章、第二章は、「できるだけ色眼鏡なしで、生まれつつあった近代なるものを、明治〜大正期の文学から読み取ろう」という準備作業。その後、「主人公」論、「固有名」論、描写論と、近代小説の各要素の成長が主題化されてゆく。個々の論点はよく整理されていてさすがだが、そのぶん、後半のまとまりが弱い気も。準備が入念だっただけに、最後はやや物足りなさが残った。「文学」の各論から「近代」の総論へ戻って締めくくってほしかった。2013/04/26
ki_se_ki
3
第五章「固有名という装置」を興味深く読んだ。/田山花袋『蒲団』を今一度読もうと思った。/そして、言語学者ソシュールの言葉。「一枚の紙の表を、裏を切り抜かずに切り抜くことは出来ない」と同時に、その「表と裏は永遠に出会わない」。この言葉、美しいなぁ。2013/03/26
-
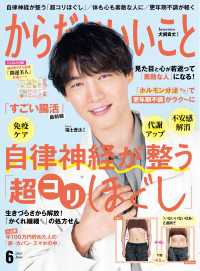
- 電子書籍
- からだにいいこと2023年6月号 から…
-
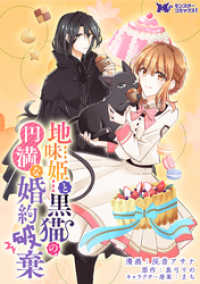
- 電子書籍
- 地味姫と黒猫の、円満な婚約破棄(コミッ…
-
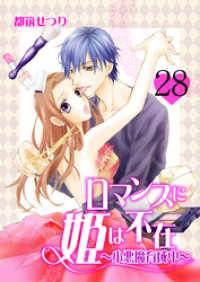
- 電子書籍
- ロマンスに姫は不在~小悪魔育成中~ 2…
-

- 電子書籍
- Mangiamo a casa マンジ…
-

- 電子書籍
- 法学教室2020年10月号 法学教室




