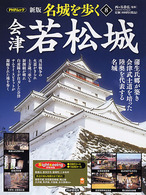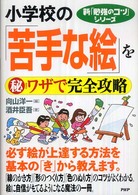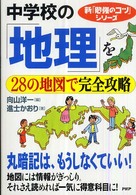- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
死体を忌み嫌い、人の目に触れないようにする現代日本の文化は果たして普遍的なものなのだろうか。中国での死体を使った民衆の抵抗運動、白骨化できない死体「キョンシー」、チベットの「鳥葬」や悪魔祓い、ユダヤ・キリスト教の「復活」「最後の審判」、日本の古典落語に登場する死体、臓器移植をめぐる裁判。様々な時代、地域の例を取り上げ、私たちの死体観を相対化し、来るべき多死社会に向けて、死体といかに向き合うべきかを問い直す。
目次
第一章 武器としての死体──中国
第二章 滞留する死体──漢族
第三章 布施される死体──チベット族
第四章 よみがえる死体──ユダヤ教とキリスト教
第五章 浄化される死体──日本
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
22
「死が存在する時、私はすでに存在しない」。だが死体だけは残る。その死体に対する考え方の違いを、日本と中国、チベット、ユダヤ/キリスト教圏の各文化を例に概観。著者の専門である中国史以外はさほど深い掘り下げでもないのだが、テーマとして充分に面白い。死体は自らを処理することができず、どうしても家族や社会の出番があるわけで、各文化の相違点もこの辺りによく表れる。近代日本の民法では、死体の相続権・処分権と家督との関わりが議論の対象になったとのこと。2025/03/03
月をみるもの
20
死体は誰のモノか? という問いは、死体がモノであることを前提にしている。死体を相続人が所有するモノだとすると、なぜそれを(臓器バイヤーに)売り払ったり、その辺のゴミ処理場に廃棄したりしてはいけないのか? すでにヒトではなくなってるから死体なのであるが、ヒトでもモノでもないのだとすると死体とは一体全体なんなのか? 答えはとうぜん時と場所によって変わるわけだが、本書で扱われる漢族、チベット、ユダヤ・キリスト教という3つの例を知るだけで、自分たちの捉え方がいかにローカルなものであるかを実感することができる。2019/06/10
はちめ
14
死体をめぐる民俗、宗教、法律などを踏まえたエッセイのような体裁なので軽く読むことができるが、内容的には簡単ではない。キリスト教文化圏における死体に対する淡泊さには触れられているが、本書には触れられていないがベトナム戦争期における米国人の遺体へのこだわりといったこともあり、そんなには単純ではないように思う。日本古代にあったと考えられるもがりも、その実態は明らかではないのではないだろうか。死体という切り口にはまだまだ研究の余地がありそうだ。☆☆☆☆★2019/08/02
itokake
13
興味深い内容で、学びの多い読書だった。図頼(とらい)はパワハラ自殺に抗議する中国の過去の習慣。これを悪用し、死体を捏造(時には殺人)し、クレイマーのようにごねる民がいた。この習慣を現代中国人は知らないはずなのに、死体を武器した事例(1988年、2008年)がある。他にも御巣鷹山の御遺体を持ち帰らなかったイギリス人など、様々な事例から人が死体をどう扱って来たのか考察する。著者の個人的なエピソードも多く、最後には宗教観があり、これが意外になるほどと思える内容だった。宗教から遠ざかってきた私にとって新鮮だった。2022/09/03
さとうしん
13
日本ではなぜ死体は隠されるのか?死体は一体誰のものか?(すなわち死体の処理を決める権利は死者本人も含めて誰にあるのかということ)そうした疑問に、中国学者でありクリスチャンである著者が取り組んでいく。日本の事例や考え方を、漢族・チベット・ユダヤ教とキリスト教のそれと比較しつつ、私たちの「当たり前」は果たして当たり前なのか?その当たり前は昔から変わりなく受け継がれてきたものだったのか?ということを考えさせる。2019/06/01