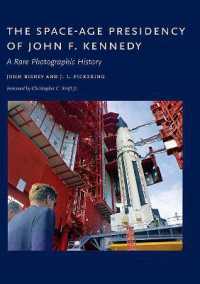内容説明
眼だけで見ているのではなく,耳だけで聞いているのでも,皮膚だけで触っているのでもない……?人工知能,モノづくりからアートまで,多分野で注目を集めるアフォーダンス理論をわかりやすく解説.ヒトをいわば「知覚システムの束」ととらえ,知性の本質に迫る.ロングセラーに20年ぶりの大改訂を加えた決定版!
目次
目 次
プロローグ なぜアフォーダンスなのか?
1 ギブソンの歩み
2 ビジュアル・ワールド
3 情報は光の中にある
4 エコロジカル・リアリズム
5 知覚システム
6 協調構造
エピローグ リアリティーのデザイン
新版あとがき
旧版あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
本詠み人
37
産業・組織心理学Ⅰのレポート課題の参考図書。ヒューマンエラーについて調べていて、エラーを防ぐデザイン原則の中でノーマンがモノのデザインに、ギブソンの唱えたこの“アフォーダンス理論”が応用されているというので大元に遡って読んでみた。この理論自体は難しいが、動けないロボットのフレーム問題はとても興味深い。△2023/07/02
zirou1984
36
新版あとがきでルンバのAI制御の例が出てきて少し驚き。英語の動詞afford(与える、提供する)を名詞化したギブソンの造語であるこの言葉の意味は「環境が動物に与え、提供している意味や価値」のことを指している。わからん。要は、生物の行動とは従来の「刺激による入力→制御→反応という出力」という中枢神経による集権的なモデルではなく、「外部環境からもたらされるイメージ→それに対する近くシステムによる」という遂次実施型モデルが実際なのではないかという話だ。難しい。130頁ほどなのにその内容はとても奥深く、興味深い。2015/09/17
Maybe 8lue
32
「わかりやすく解説」というので読んでみたが「わかりませんでした」私はまだまだ「形」を放棄出来ていないのかなぁ。冒頭のロボットIは、現在のようになるまで何台が犠牲になるのか(笑)読み返す気力もないので、アフォーダンスを説明してくれる本をまた探そう…2016/07/29
りょうみや
29
主に視覚認知の研究からアフォーダンスの概念を導いている。正直アフォーダンス自体は分かったようで分からない。環境を丸ごと受け取る情報処理のイメージ。人間は単なる一枚の画像からではなく、自分からの働きかけ・移動を含めて環境全体の情報を使って空間を認知しており、その凄さはよく伝わってくる。確かに限定された環境でしかうまく動作できない人工知能(フレーム問題)と生物の大きな差が感覚的にも理解できる。2022/07/19
zoe
23
メモです。アフォーダンスとは、環境が動物に与え、提供している意味や価値。空気、物質、面で構成される。知覚の結果として、我々は自分に関係することと無関係なことを効率的に見分けている。ロボットをプログラムで動かそうとすると容易でないことが分かる。これを「フレーム問題」と呼んでいる。移調しても同じメロディーに聞こえる。単なる光の点滅が光の移動に見える。変化の中に、不変を見出すということ。変化項は変えられるが、不変項は制御できないことを知る。リアリティーを知り、アフォーダンスを知覚する。2019/06/23
-

- 洋書
- Into the War
-

- 電子書籍
- 聖女は罪を赦さない 9話「さあ、どうぞ…