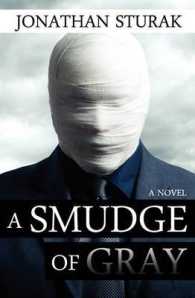内容説明
数十年の長きにわたって、この国をがんじがらめにしてきた岩盤規制。一九八〇年代の土光臨調以来、昨今の獣医学部新設問題まで、それを打ち砕く試みは繰り返されてきたが、道はまだ半ばだ。なぜ岩盤規制は生まれ、どのように維持され、今後の日本経済の浮沈にどうかかわるのか。そして、官僚とマスコミはこの旧弊をどう支えたのか。現場の暗闘を知るトップブレーンが、改革の現状と未来をわかりやすく指し示す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HMax
29
「既得権維持を求め、関係議員に働きかけ、官僚がこれに従う。」、三方よし。「何か新しことをしようと思えば、いちいちお役所にお伺いをたてなければならない。」全くばかげた話し。それもわざわざ「東京まで来い」というのだからひどい。「事前規制」からの脱却が必須。アフリカの話しかと思っていたが日本でも「リープフロッグの可能性」があるというのが面白い。20年以上議論を続けるうちに、米国か中国かが次世代技術を開発し、それに乗っかるチャンス到来を待つべきか。とにかく変な規制が多い。巻末に変な規制リストを作って欲しかった。2019/08/15
kawa
26
長年、霞が関の岩盤規制に対峙してきた著者による改革実態史。改革を阻む抵抗勢力は政・官・財、鉄のトライアングルと視聴率重視のマスコミとの共犯関係にあるとのご宣託。全て例外なしはともかく「事前規制型」から「事後チェック型」は、大きな流れなのだろう。が、「事後型」の問題点やその対処法も知りたいところ。「モリカケ」の実像、行政内部者の業務遂行ルールである「通達」があたかも法律のごとく国民を拘束している実態(大事なルールほど下位規範で)、大臣は「一日警察署長」のようなもの等、興味深い記述が多数。2023/06/23
hk
20
「日本以外の先進国において規制緩和は1990年代に解決済みの問題である。これらの先進国では所得格差や移民問題が新たな問題になっている。日本だけが規制緩和という前世紀の課題で躓いたままだ」といったニュアンスで著者は語る。 だがどうだろうか? 節操なく規制緩和を行ったから先進国では経済格差や移民の問題が生じたのではないのか。規制緩和は問題そのものではなく手段なのではないのか。などなど著者の主張には違和感を禁じ得ない。規制緩和を不景気下で行ったがために、日本は30年にも及ぶ景気低迷を続けているのではないのかな。2019/06/07
しゅわっち
18
規制改革の歴史と現状が良くわかる本でした。 電力が規制改革されても 業界、族議員、官僚、マスコミで 守られていたと思う。 天災で状況で変わった事に不思議さを感じる。 著者はメディアにはあまり出ないと思う。 メディアからすれげ電波オークションの中心人物と思われているのだろう。読んでいて 時代がメディアがやりたい放題していたのを許さないように感じた。ハードとソフト分業化が 時代の流れに感じた。大学の補助金での癒着も学生にとって良い方向に進んでほしい。 2020/09/21
ステビア
17
どんどん規制取っ払ってくれ〜2021/04/29
-
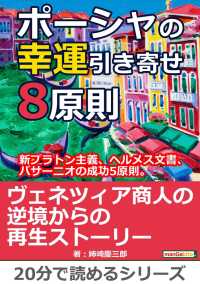
- 電子書籍
- ポーシャの幸運引き寄せ8原則、 - 新…